 美容と健康
美容と健康 【書評】「育ちが良い人」続編!「オバサン」と「若い子」の境界線
「オバサン」と「お姉さん」の境目はどこだろうか。 年齢? シワやたるみの量? それとも……。 重力に負けるな、力を入れろ。 年齢とともに日々刻々と減ってゆくもの。 それは「筋肉量」。 筋肉の量が減るともちろん痩せにくくもなるし、真っすぐ立っ...
 美容と健康
美容と健康 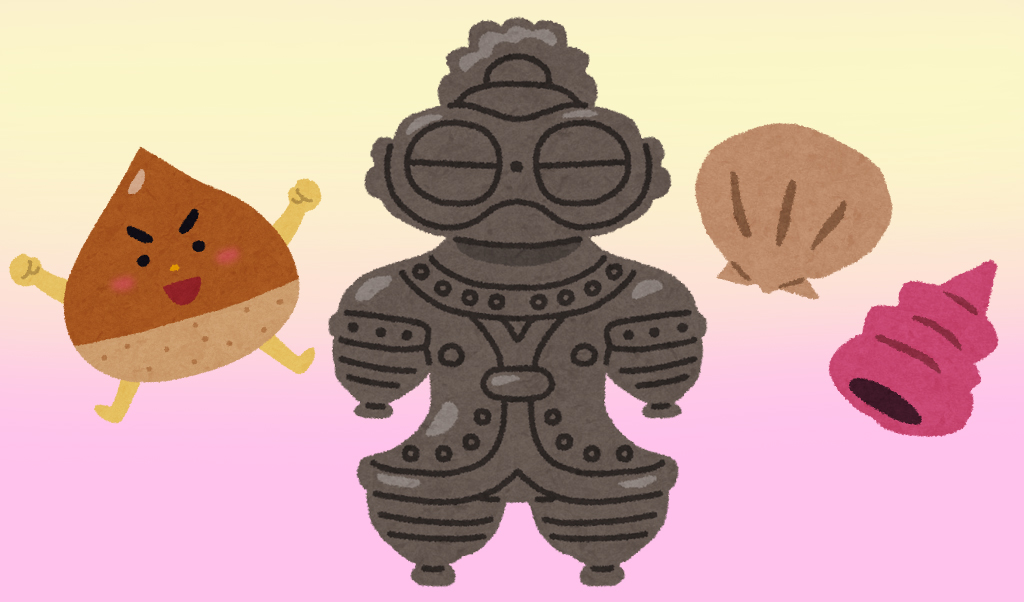 20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史 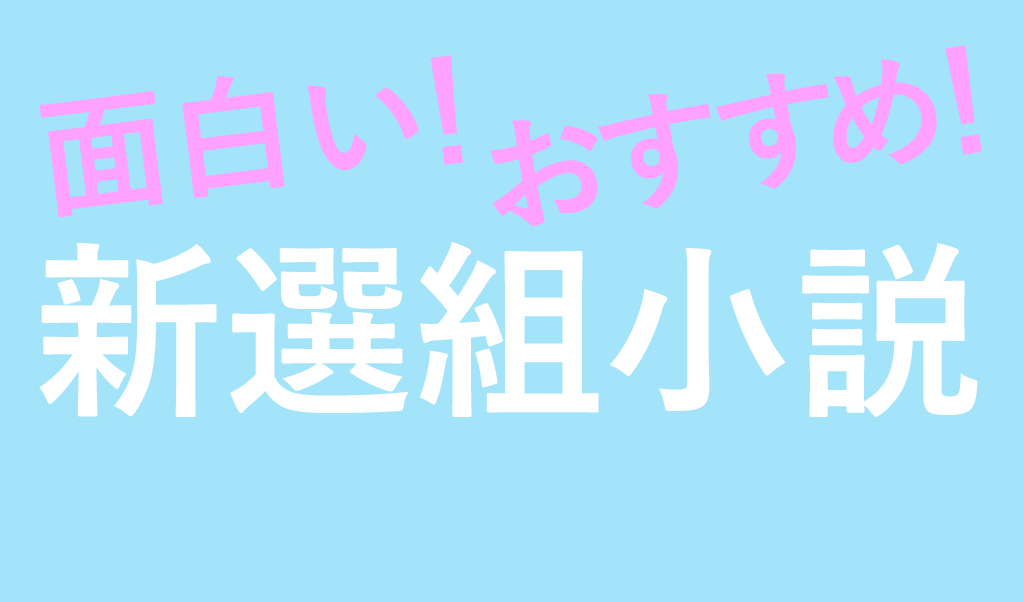 90 文学
90 文学  40 自然科学
40 自然科学 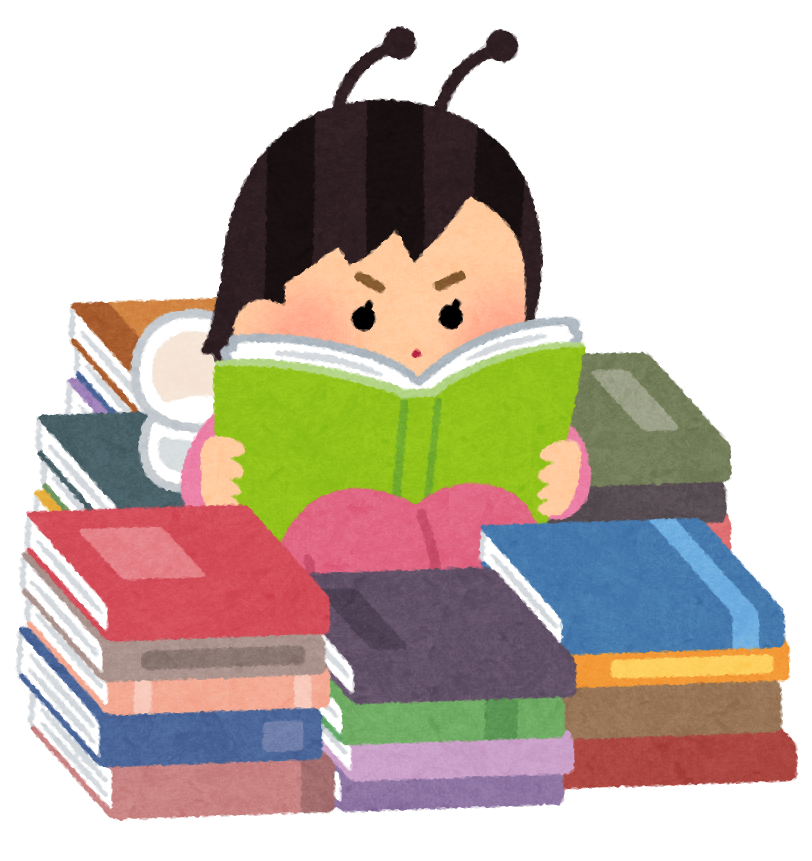 60 産業
60 産業