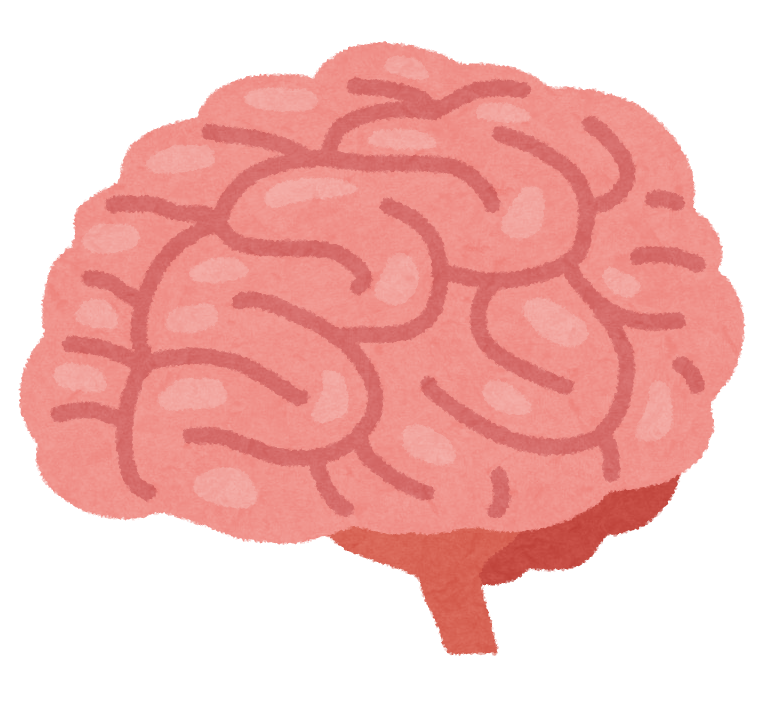 40 自然科学
40 自然科学 [レビュー]「最強脳」の作り方 スマホ脳先生の特別授業
脳にとって最強の訓練は、運動らしい。 それはもう、やっぱりそうらしいのだ。 そのへんは、『脳を鍛えるには運動しかない!』という、そのまんまのタイトルの本なんかに詳しい。この本では、特に有酸素運動(つまりジョギング)の有用性が書かれている。 ...
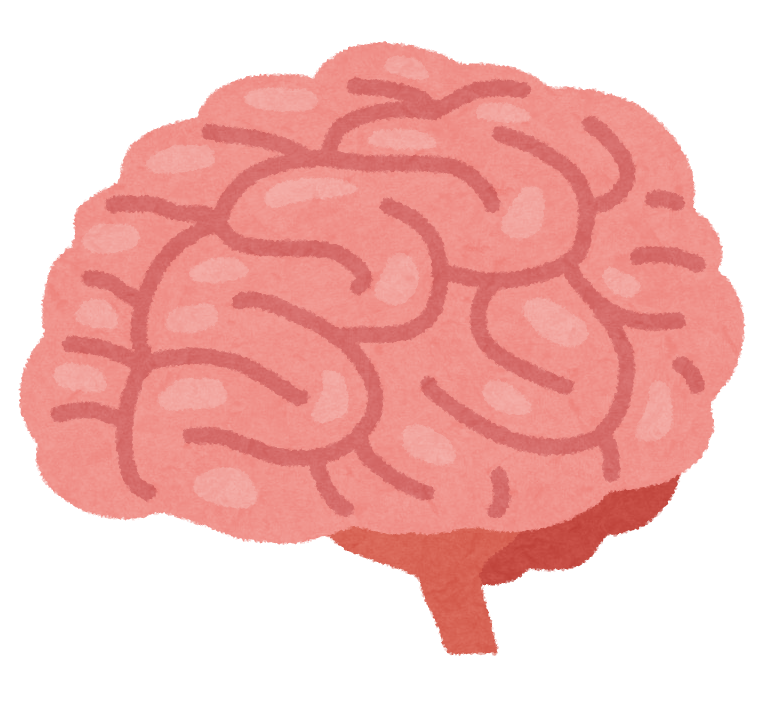 40 自然科学
40 自然科学  10 哲学
10 哲学  20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史  勉強法
勉強法  90 文学
90 文学