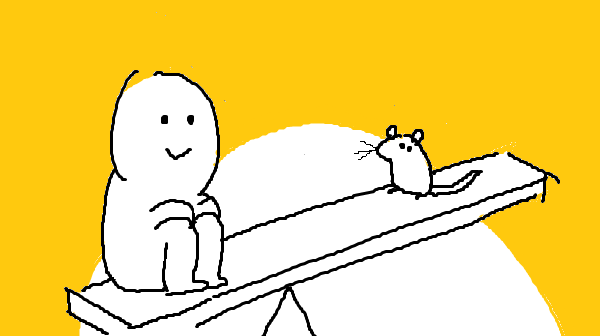 お金
お金 『レバレッジ・シンキング』|楽して大きな成果を手に入れろ
こんにちは。「怠けるための努力は惜しまない」がモットーの あさよるです。これを言うと、冗談だと思って笑う人か、同意してくれる人か、「それはおかしい」と反論する人の3つに分かれます。最後の「それはおかしい」というのは「楽をしたいという発想は良...
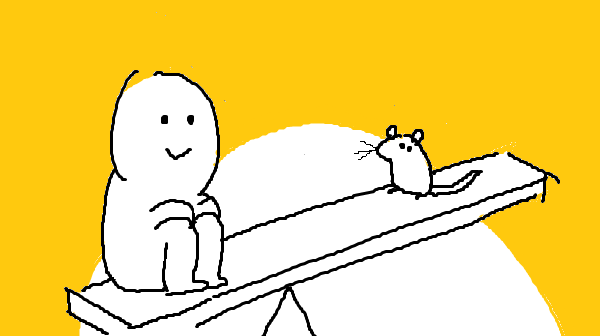 お金
お金  アイデアの出し方
アイデアの出し方  00 総記
00 総記