以前、山内昶さんの『タブーの謎を解く』を読み、ブログでも紹介しました。各文化が持っているタブーは、食と性に関するものが多い。それは、ヒトは〈自然界〉という〈混沌〉から抜け出し、〈文明社会〉という〈秩序〉をつくり出しても、我々自身が自然であり混沌を内に宿している。それが生命としての営みである〈食〉であり〈性〉である。自分のまわりから混沌を排除すればするほど、どんどん自分の混沌が際立っていく様子が面白く読了しました。
同著者『「食」の歴史人類学』も、以前から積読してあり、雨が降りしきる午後やっと手が伸びました。
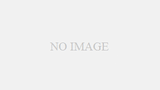
異国料理を食べる?拒否る?
現在の日本人が伝統的だと感じるメニューも、よくよく見ると外国から流入した食品が数多く使われています。サツマイモやカボチャはアメリカ原産で、ゴボウも外来種。ニンジンの原産はヨーロッパ、北アフリカ、小アジアらしく、室町時代に来日したそう。世界中の食品が日本にもなだれ込んで来ていることが分かります。
また、食品である植物が入って来るということは、栽培方法や農機具も必要です。文化が行きかっていると考えられますね。
そして、人々が異国の食べ物とどのように対峙してきたのか。記録に残ったものが紹介されています。
日本人が出会ったヨーロッパの食事
戦国時代にヨーロッパへ渡った天正遣欧使節の一行が、行った先々での食事の様子が記録されています。彼らは様々な肉料理にはあまり手を付けない。口にしても鶏肉のみ。食事中は熱い湯を飲み、珍しがられています。他に人がいないときは、二本の棒を使い巧みに食事をします。
また、使節団の談として、日本の貧しい食品と違い、ヨーロッパは豊かな土地だと称しています。天正遣欧使節の面々は、戸惑いつつもそれなりにヨーロッパの食事になじもうとしていたようです。
ヨーロッパ人が出会った日本の食事
日本人は肉食を行わず家畜を食べない。米や豆を食べる。イエズス会のザビエルは、
日本の食生活はきわめて貧しいので、やむを得ず粗食に甘んじなければならないが、神に仕える身にとっては、かえって節制、禁欲のきびしい苦行生活を送ることになり、アニマの浄化と宿徳のためには好都合である。
p92-93
粗食ながら健康で、高齢になるまでみなが生きていることを記しています。
しかし、多くのバテレンたちは、日本の粗食に困っていたようです。味付けも淡泊で、生魚を出されることが苦痛だった様子です。生魚を食べないからといって怒りはしないが、バテレンたちが生魚を食べると日本人が喜ぶので、食べざるをえないそうで、昔の異国人同士なのに、人間味のある話だなぁと他人事なので思いますw
日本人はヨーロッパ食に慣れるのに、ヨーロッパの人は日本の食事に慣れないようですね。食の異文化の話はかなり面白いので、ぜひご一読を。
食のタブー
そして、食にまつわる「タブー」のお話。
現在の日本では昆虫食は一部を除きタブーのようになっています。しかしに、ヒトが樹上で生活をしていた時代は虫を食べていたのですから、由緒あるのは昆虫食。
サルを食べてもいいか?動物の内臓を食べてもいいか?手づかみで食べてもいいか?
食に関するタブーは、〈野蛮〉な感じと〈文化的〉な感じの間で起こるようです。
(ちなみに あさよるは魚の頭を食べられません。シシャモとかメザシとか、頭からバリバリ食べる系がムリです。次いで、骨ごとバリバリ食べる系が苦手。アジの天ぷらとかね。これはあさよる的に「野蛮な」感じがするのだろうか?しかし、不思議とエビやカニは大丈夫なので「甲殻類はイケる」と思っています。ということで、あさよる的には、魚の頭よりは昆虫の方が食べられそうな気がします。美味しいのかわからないけど。すごくどうでもいい話ですがw)
フォークとナイフを使う西洋人は、手づかみで食事をする文化を「野蛮だ」と感じるそうですが、中国人は食卓にナイフを持ち込む西洋人を野蛮に思う。中華料理は早々と食卓からナイフを排除したからです。食卓のナイフは危険で、防具をはめて食事をしなければならなかったそう。道具にもタブーがある。
食のタブーを語るにはやはり信仰の話もせねばなりません。「食」というのはなんと根源的であり、あらゆる物事と絡み合っていることでしょうか。
ガストロノミー
ガストロノミーとは、料理を中心として、様々な文化的要素で構成される。すなわち、美術や社会科学、さらにはヒトの消化器系の点から自然科学にも関連がある。
(中略)
ガストロノミーを実践する人を、食通あるいはグルメなどと呼ぶが、彼らの主な活動は、料理にまつわる発見、飲食、研究、理解、執筆、その他の体験にたずさわることである。料理にまつわるものには、舞踊、演劇、絵画、彫刻、文芸、建築、音楽、言い換えれば、芸術がある。だがそれだけでなく、物理学、数学、化学、生物学、地質学、農学、さらに人類学、歴史学、哲学、心理学、社会学も関わりがある。
キリシタンの時代、ヨーロッパの文化が世界中に広まったのは同時に、ヨーロッパへ世界中の食文化が流入した時代でもあります。西洋人は聖書の規律を守るため、異食文化に抵抗しますが、止められません。アメリカ大陸原産のポテトは、西洋がアメリカ大陸を侵略したのと同じように、西洋の食文化になくてはならない食材になりました。
食文化を追うことは、世界の文化、歴史、宗教、植生、哲学などなど、人の活動すべてを追うことなのかもしれません。〈食〉があまりに根源的で、あまりに動物的である限り。
あまりにも途方もない世界をのぞき込んでしまった気分。満腹です。
「食」の歴史人類学―比較文化論の地平
目次情報
食前酒(アペリティフ)に
日本料理の国際性 家康とてんぷら 食文化革命としてのキリシタン紀
Ⅰ 日本人と異国料理
一 国内で
1 インド料理とアンジロウ
『鉄炮記』の飲食情景 アンジロウとザビエル 理性的な日本人 アンジロウは何を食べたか 五峯とは海賊王直
2 地中海料理と天正少年遣欧使節
派遣の目的 デウスは商人の神 四少年は何を食べていたか 文化相対主義
3 フランス料理と伊達遣欧使節
疑惑の使節 白紙委任の政宗の新書 迷惑の使節 ソテーロのゆすりとたかり 支倉長経は何を食べたか
二 国内で
1 国際文化都市府内
アンジェラスの鐘が鳴る 肉飯の大盤振舞い
2 洋食好きの殿様たち
殿は何を食べたか オランダ正月献立
Ⅱ 南欧人と日本料理
一 青い目に映った日本の食事情
1 最初の日本情報
アルヴァレスの報告 一日三食はいつからか ランチロットの情報 ザビエルとダイエット料理 粗食に悩むバテレン 適応の文化差
二 文化衝突とマナー摩擦
1 手食/非手食
手食する西洋人 右手と左手 ナイフの攻撃性 フォークの使い始め 目的別の食具と箸の万能性 料理の人工性と自然性
2 「創世記」のコスモロジー
人間中心主義 西洋ロゴスの土入ロードリーゲスのみた茶の湯の精神
3 自文化強制か異文化順応か
アメリンドの民族大虐殺(ジェノサイド) 日本文化に対する態度 順応主義とその矛盾 デウスに従うか主君に従うか
Ⅲ 雑食動物ホモ・サピエンス
一 雑食・肉食・菜食
昆虫食 サルからの贈り物 肉食/菜食率
二 西洋の肉食
1 ローマの食卓
破壊的料理 トリマルキオの饗宴
2 コーモスの祝宴
ラブレーの食欲讃歌 小説から現実へ ローマ市の盛宴 ルイ一四世のすさまじい胃袋
3 生きていたポトラッチと野生
客人歓待制度 不潔な食卓、粗野なマナー 差異の体系
4 ガストロノミー革命
征服されたヨーロッパ ヌーベル・キュイジーヌの出現 ロシア式サーヴィスの導入 テーブルと銘々膳
三 日本の肉食
1 古代の肉食
食物発生神話 古代王の狩猟 『万葉集』とモツ料理 平安朝の肉食
2 中世の肉食
武家・僧侶の肉食 謎の呪文 公家の食域 いかもの喰い
3 近世の肉食
いぜん健啖な庶民 大名の狩猟と贈与 江戸期の肉食 将軍と牛肉 肉食のすすめ
Ⅳ 食物タブーと文化理論
一 タブーの展開と構造
1 日本のタブー
サルを食う 漁(すなどり)も禁止 寺苑で屠殺 諸社服忌令
2 西洋のタブー
複雑怪奇なタブー ただ一つウマが ペット・タブー
3 タブーの通念
宗教のせいか 実利のためか
二 食べるによい理論と考えるによい理論
1 食べるによい学派
ハリスの文化唯物論 ユダヤ人とイナゴ ヒンドゥ教徒とウシ イスラム教徒とブタ
2 考えるによい学派
リーチの文化記号論 ダグラスの文化象徴論
3 タブーの体系
領界(リージョン)と境界(リーメン) カニバリズムの恐怖
4 タブーの比較文化論
変身譚 異類婚 獣姦その他 文化の統合理論にむけて
食後酒(デイジエスティフ)に
料理の三角形 女性原理/男性原理
勝手話
参照文献
山内 昶(やまうち・ひさし)
1929年東京生まれ。京都大学文学部(仏文専攻)、同大学院(旧制)卒、パリ大学高等研究院に留学。現在、甲南大学教授。人類学・比較文化学。
著書:『ロマンの誕生』(論創社)、『経済人類学の対位法』(世界書院)、『現代フランスの文学と思想』他
訳書:サーリンズ『石器時代の経済学』(法政大学出版局)、ゴドリエ『人類学の地平と針路』(紀伊国屋書店)、アタリ『所有の歴史』(法政大学出版局)、ロダンソン『イスラームと資本主義』(岩波書店)他。
論文:「フランス絵画とジャポニズム」「王権と転倒儀礼」「食=性タブーの文化学」他。



コメント
[…] 記事リンク:『「食」の歴史人類学―比較文化論の地平』|それ、食べる?拒否る? […]
[…] 『「食」の歴史人類学―比較文化論の地平』|それ、食べる?拒否る? […]
[…] 『「食」の歴史人類学―比較文化論の地平』|それ、食べる?拒否る? […]
[…] 『「食」の歴史人類学―比較文化論の地平』|それ、食べる?拒否る? […]