 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学 『正直、服はめんどくさいけれどおしゃれに見せたい』|not無難のテッパンコーデ
「花より団子」と言いますが、わたしの場合は花より虫やカエルを追っかける娘時代を過ごしたもので、おしゃれには縁のない人生を送ってきた。それが30代に差し掛かり「こりゃいかん」とおしゃれに関する本を読みかじるようになった。最近なんて、ファッショ...
 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学  40 自然科学
40 自然科学 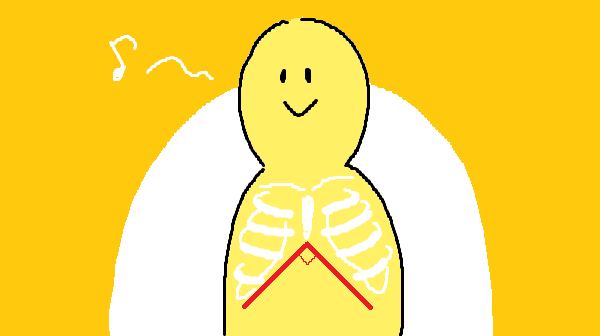 40 自然科学
40 自然科学 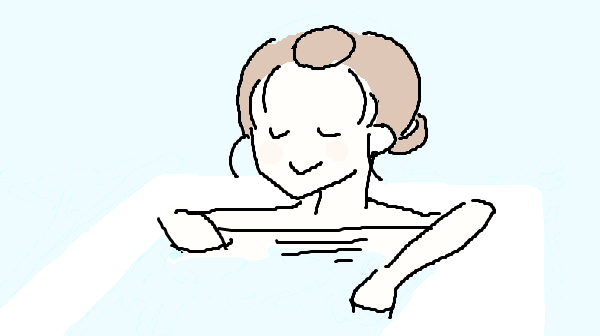 40 自然科学
40 自然科学  美容と健康
美容と健康