 10 哲学
10 哲学 『医師が教える幸せな人がやめている36の習慣』|やっぱり「当たり前」が一番大事
こんにちは。気分が落ち込みがちな あさよるです。今の時期、気づいたら外が暗くって「ああ、なにもしないまま一日が終わってしまう」と思いがちです。朝も、なかなか体を起こせなくて困っています。布団と体が一体化しているんですね(;'∀') 生活習慣...
 10 哲学
10 哲学 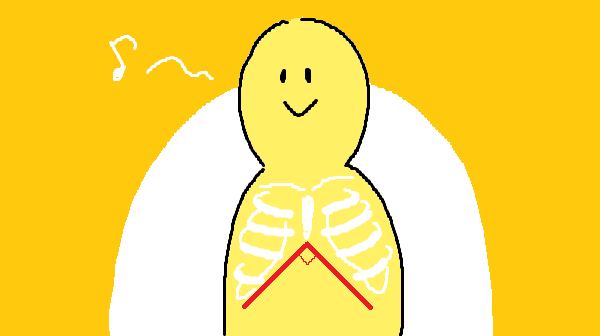 40 自然科学
40 自然科学 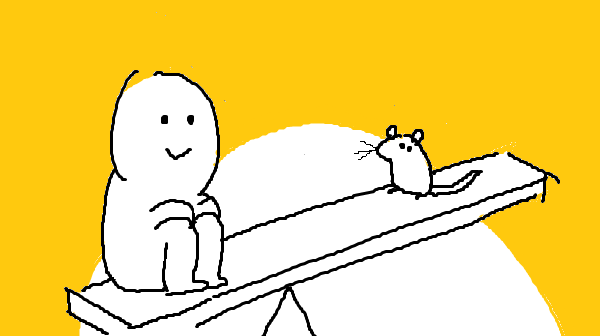 お金
お金 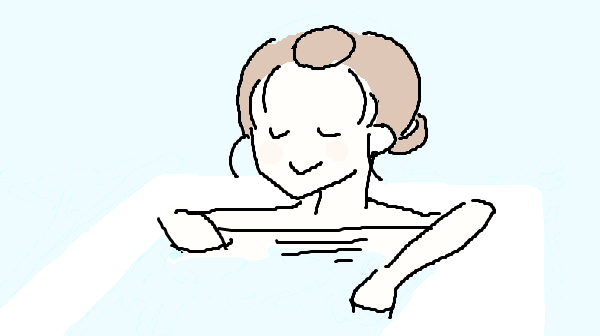 40 自然科学
40 自然科学 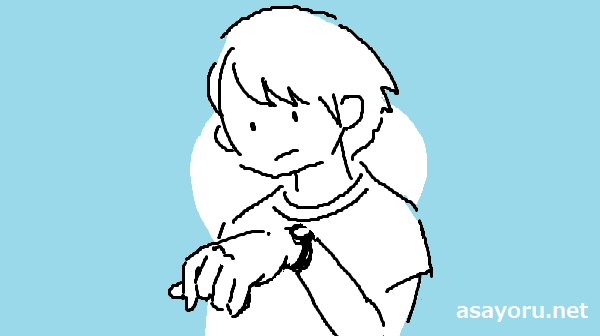 仕事に役立つ本
仕事に役立つ本