 10 哲学
10 哲学 内田樹『日本辺境論』|田舎者でゴメン(・ω<) テヘペロは強い
こんにちは。本は寝かしまくる あさよるです。大体、人からおすすめされると、3年スパンくらいで着手し始めます。一応、読むのは読む。いつになるのかわからないけどね…!という感じ。そして、積みまくったのが内田樹さんの『日本辺境論』です。二回の引っ...
 10 哲学
10 哲学  00 総記
00 総記  10 哲学
10 哲学 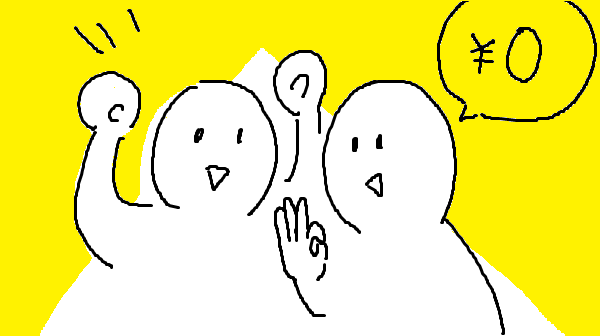 10 哲学
10 哲学  10 哲学
10 哲学