 70 芸術、美術
70 芸術、美術 落語が文学に与えた影響とは?『落語速記はいかに文学を変えたか』が解き明かす近代文学史
桜庭由紀子『落語速記はいかに文学を変えたか』は面白い本だった。 落語が明治期の日本語の言文一致運動で重要な役割を果たしたことを紹介する内容だ。 日本語の変遷の話ではなく、あくまでも「落語」の本。 落語好きには一読の価値ある一冊です。 圓朝の...
 70 芸術、美術
70 芸術、美術 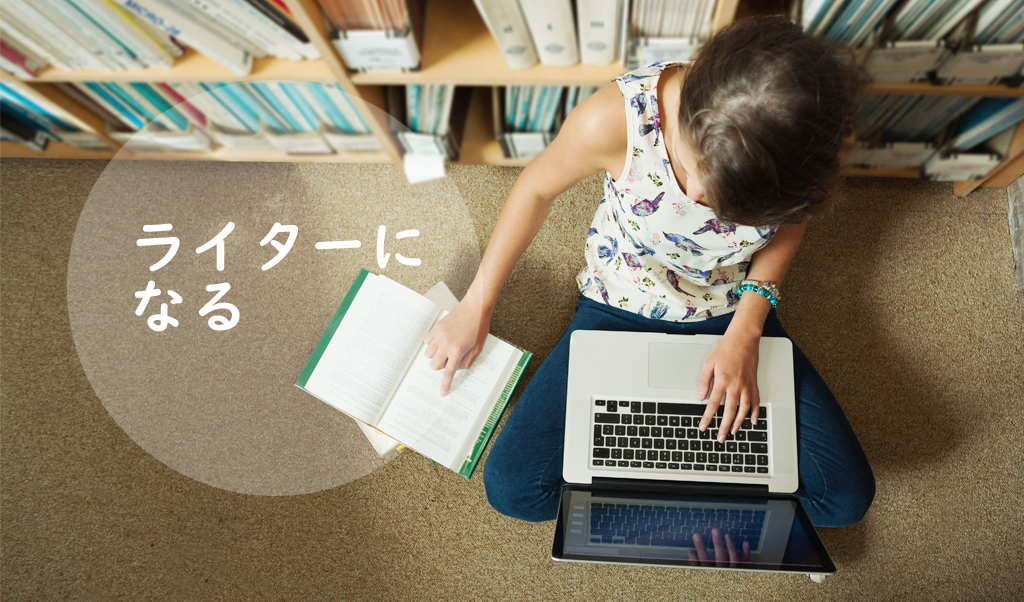 70 芸術、美術
70 芸術、美術  70 芸術、美術
70 芸術、美術  70 芸術、美術
70 芸術、美術  30 社会科学
30 社会科学