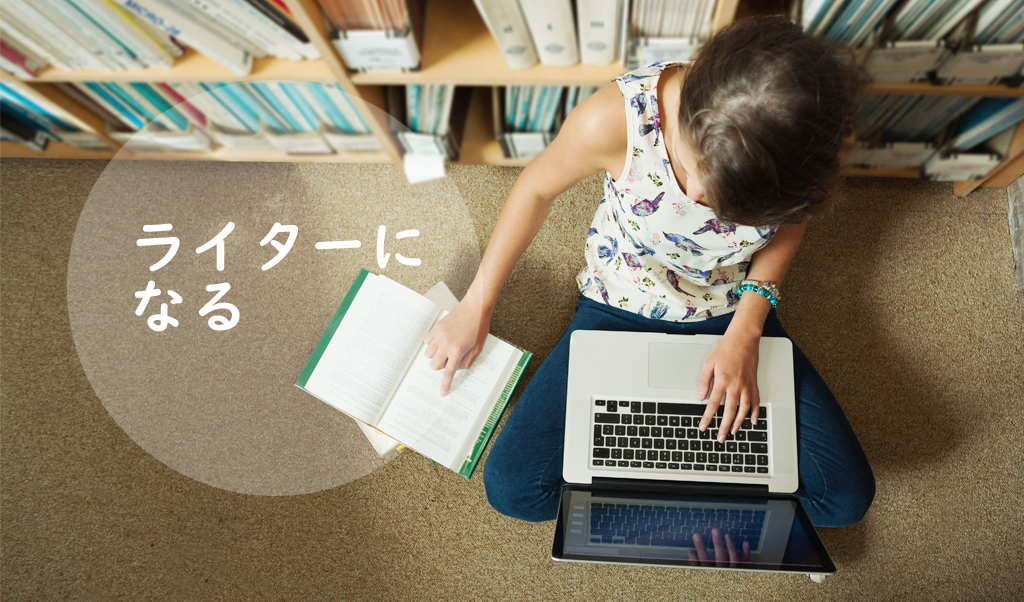 70 芸術、美術
70 芸術、美術 音楽ライターになろう! 情熱と才能を活かすためのガイドブック【好きを仕事に】
自分の「好き」を言葉にして、多くの人に伝えられたら……。 きっと今よりより豊かな人生になるだろうなあなんて思います。 しかし考えてみると、今は誰もが常にインターネットに繋がっていて、SNSやブログですぐに発信できる時代。 もう準備は既にでき...
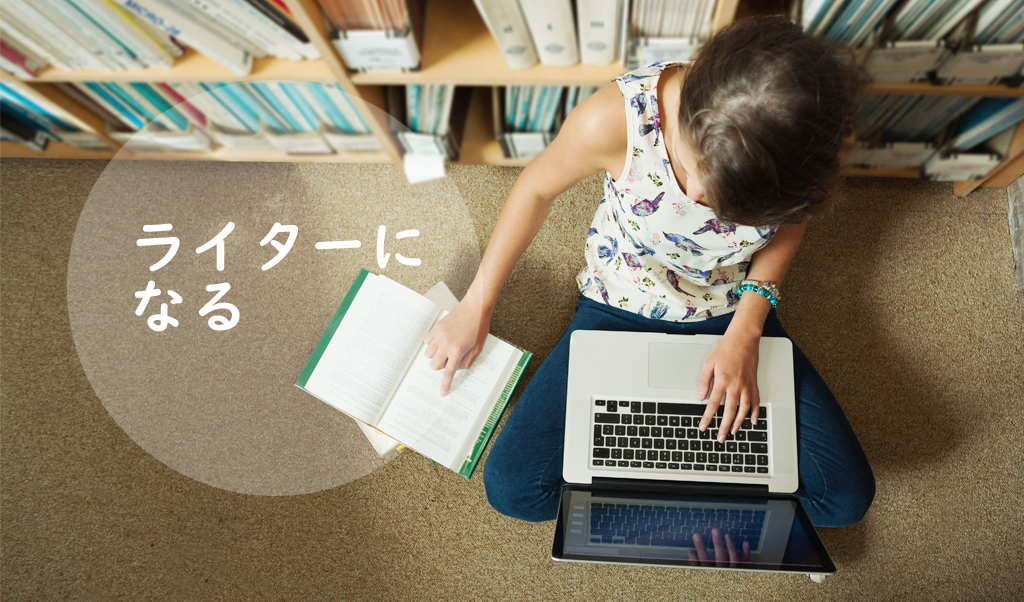 70 芸術、美術
70 芸術、美術 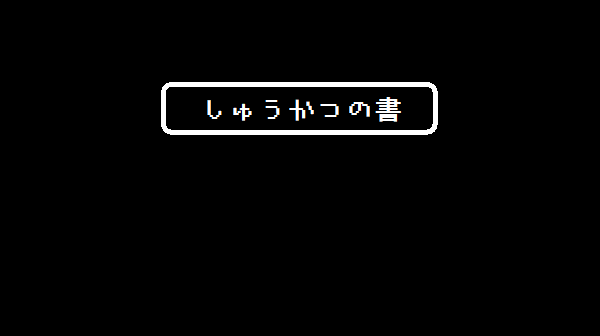 仕事に役立つ本
仕事に役立つ本 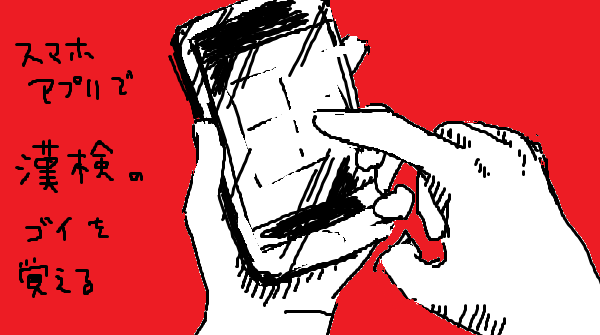 80 言語
80 言語  10 哲学
10 哲学  オシャレ
オシャレ