 10 哲学
10 哲学 『心配学』|原発、喫煙、ギャンブル、災害……本当に心配すべきこととは?
「〈安全〉よりも〈安心〉が欲しい」みたいな言い回しがあるように、不安な気持ちが続くのはつらい。大丈夫と安心していたいものだ。本書『心配学』は、災害やテロ、事件、事故など心配事を、正しく心配するためのガイドラインになる良書だ。 〈適切に心配す...
 10 哲学
10 哲学  10 哲学
10 哲学 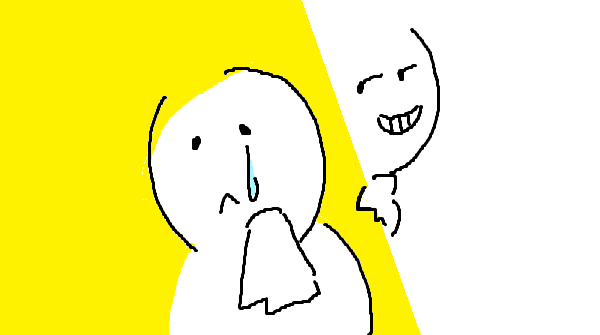 10 哲学
10 哲学 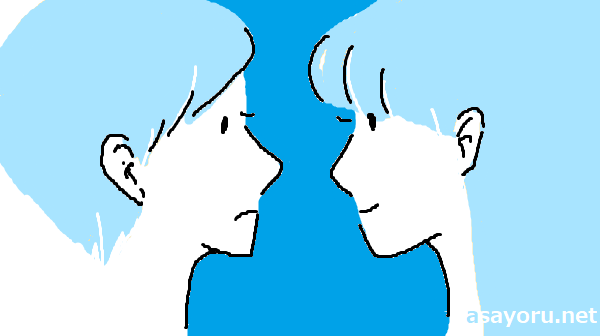 10 哲学
10 哲学  10 哲学
10 哲学