 40 自然科学
40 自然科学 すごい!左利きの特徴
こんにちは。あさよるです。 わたしは右利きなので、左利きの人ってちょっと不思議な存在です。 左利きの人は、全体の1割しかいないそうです。 想像よりも少ない数字ですね。 さらに、右利きの人とは脳の使い方も違っているので、左利きの人の特徴もある...
 40 自然科学
40 自然科学 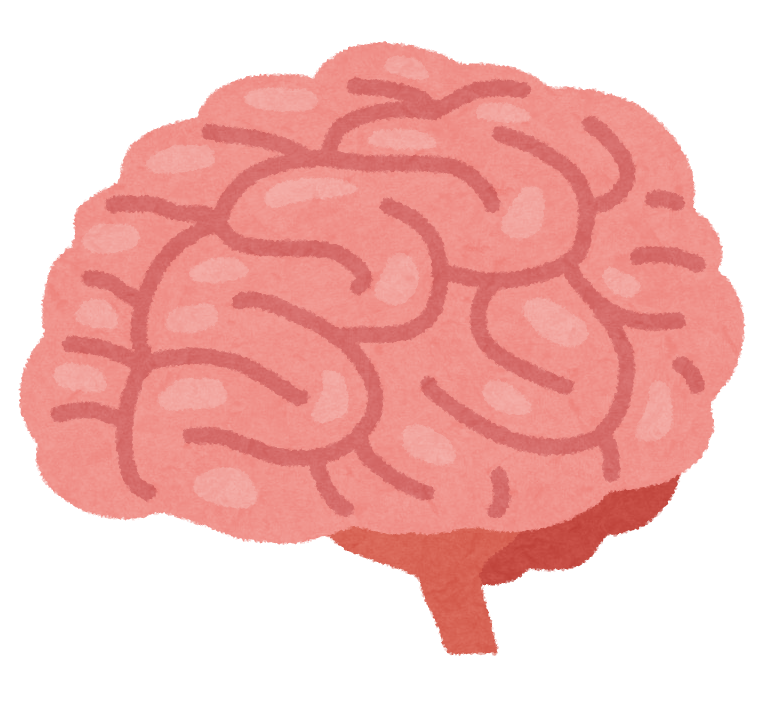 40 自然科学
40 自然科学  40 自然科学
40 自然科学  10 哲学
10 哲学  20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史