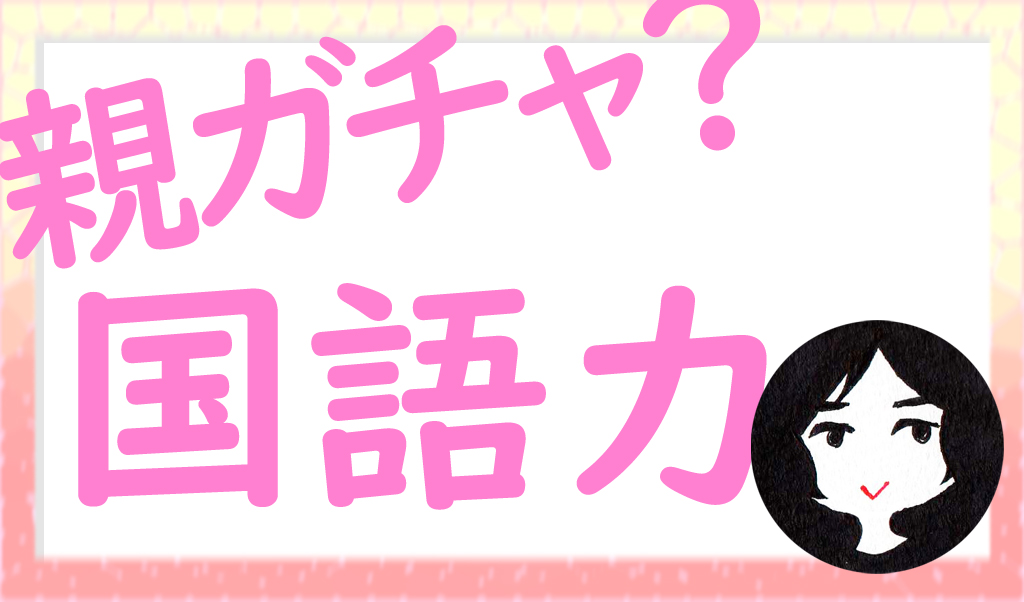 30 社会科学
30 社会科学 【レビュー】親ガチャ?教育格差?「誰が国語力を殺すのか」
少し前に「ごんぎつね」を誤読する子どもたちの話題がバズったのを覚えているでしょうか。 記事リンク:『ごんぎつね』の読めない小学生たち、恐喝を認識できない女子生徒……石井光太が語る〈いま学校で起こっている〉国語力崩壊の惨状 | 文春オンライン...
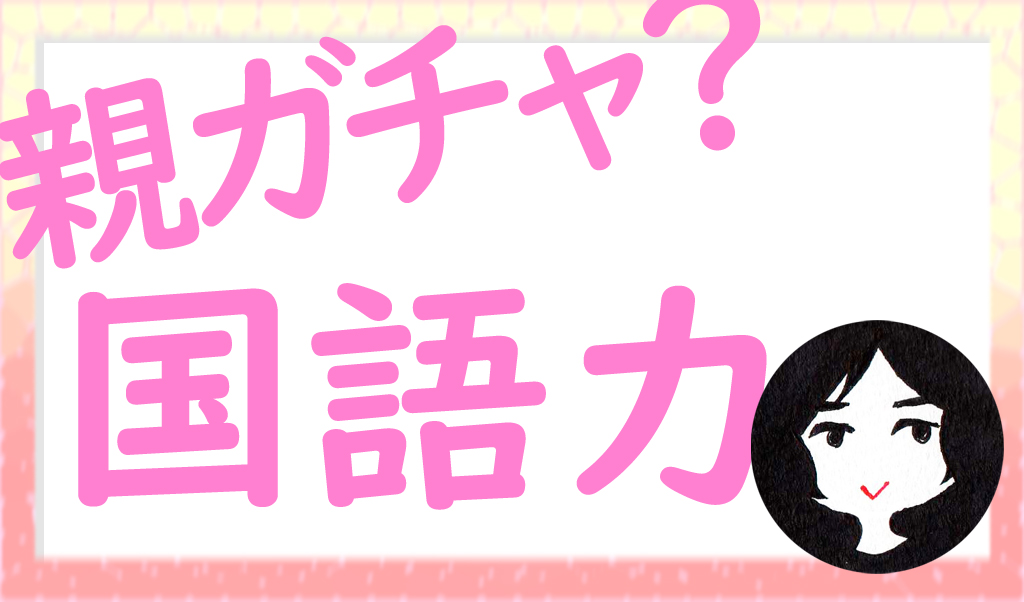 30 社会科学
30 社会科学  60 産業
60 産業