 30 社会科学
30 社会科学 『ビジネスメイク術』|信頼される身だしなみ術
「身だしなみ」は信用にかかわるもの。 ビジネスの場では、服装だけじゃなく化粧だって、やりすぎも、やらなさすぎも場違い感がある。 化粧がふさわしくないから、商談の場や、緊張感のあるシーンに立ち会えない場合もあるらしい。 まぁ、わかるよね。 見...
 30 社会科学
30 社会科学 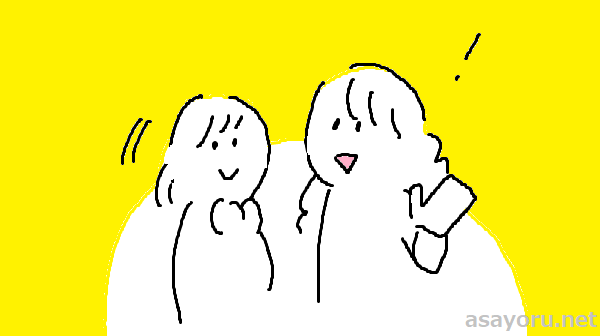 コミュニケーション
コミュニケーション  10 哲学
10 哲学 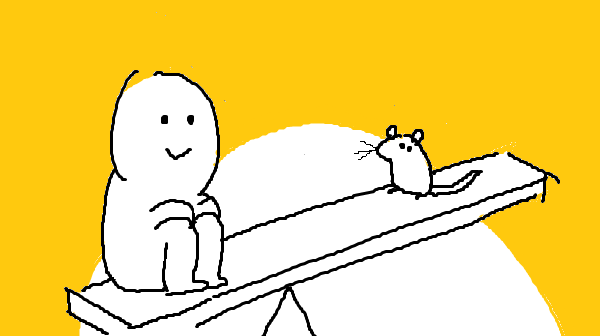 お金
お金  やる気の出る本
やる気の出る本