 90 文学
90 文学 まさかの裏切り?!『ドクタケ忍者隊 最強の軍師』で描かれる土井先生の”もう一つの顔”
わたしは『忍たま乱太郎』をふつうに子ども時代に見ていただけで、いや、学生時代録画して見ていたけれども……しかし、その程度で、特に強い思い入れがあるタイプではないんだけれども……。 2024年12月公開の『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊...
 90 文学
90 文学  90 文学
90 文学  40 自然科学
40 自然科学  10 哲学
10 哲学 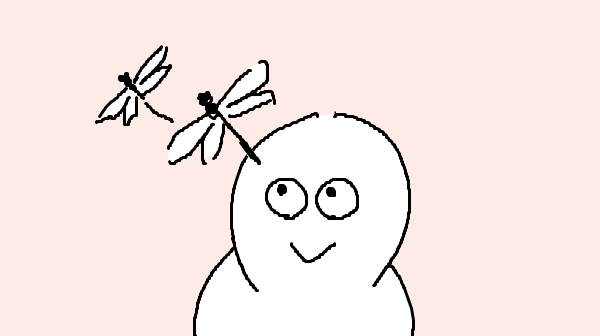 78 スポーツ、体育
78 スポーツ、体育