 90 文学
90 文学 立川談春『赤めだか』|落語を知らない人にもめちゃ面白い
こんにちは。落語が好きな あさよるです。 今回、『赤めだか』を読んだんだけど、きっかけは、米津玄師さんの『死神』のMVだったのかもしれない。 これきかっけで、YouTubeで「死神」の動画なんかをいくつか見まして、その流れで、「落語と言えば...
 90 文学
90 文学  10 哲学
10 哲学  90 文学
90 文学  90 文学
90 文学 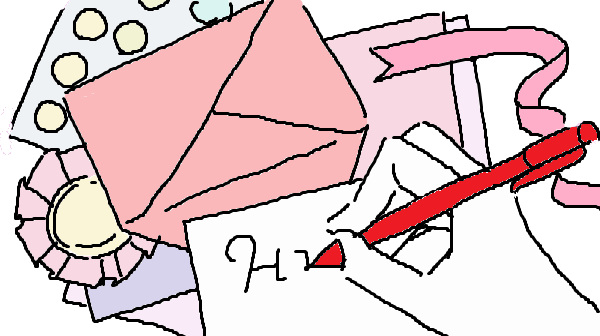 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学