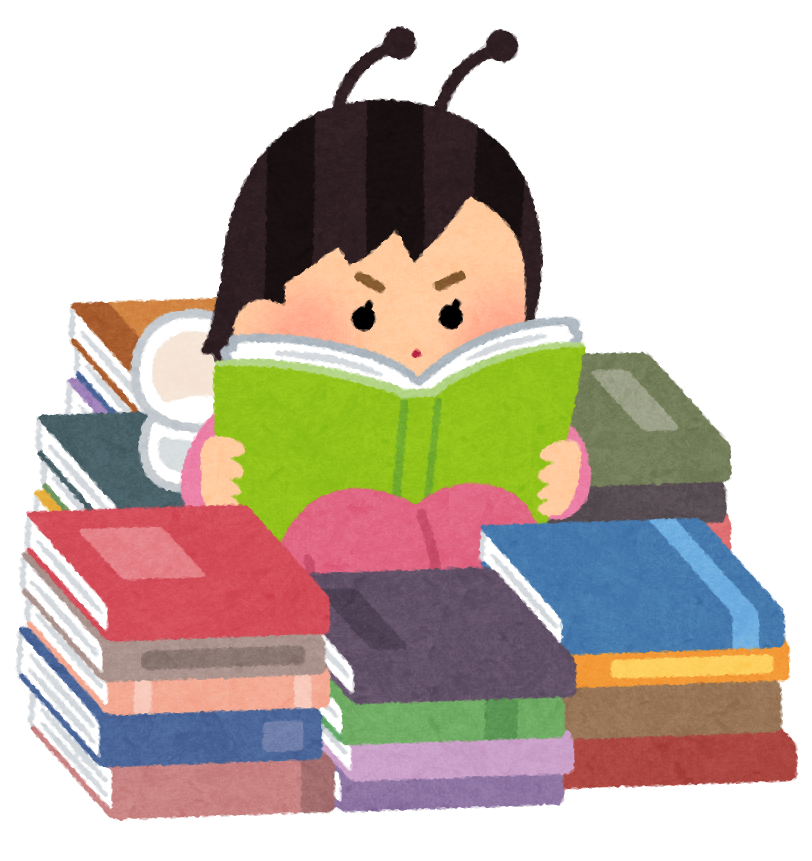 60 産業
60 産業 [書評]テレビリサーチャーという仕事
「テレビリサーチャー」という仕事があるらしい。 簡単に言っちゃえば、テレビ制作にあたり、番組のネタの裏取りをするのが主な仕事だ。 テレビという華やかな世界を支える、地味だけど大事な裏方の仕事なのだった。 「調べる」ことが仕事 バラエティー番...
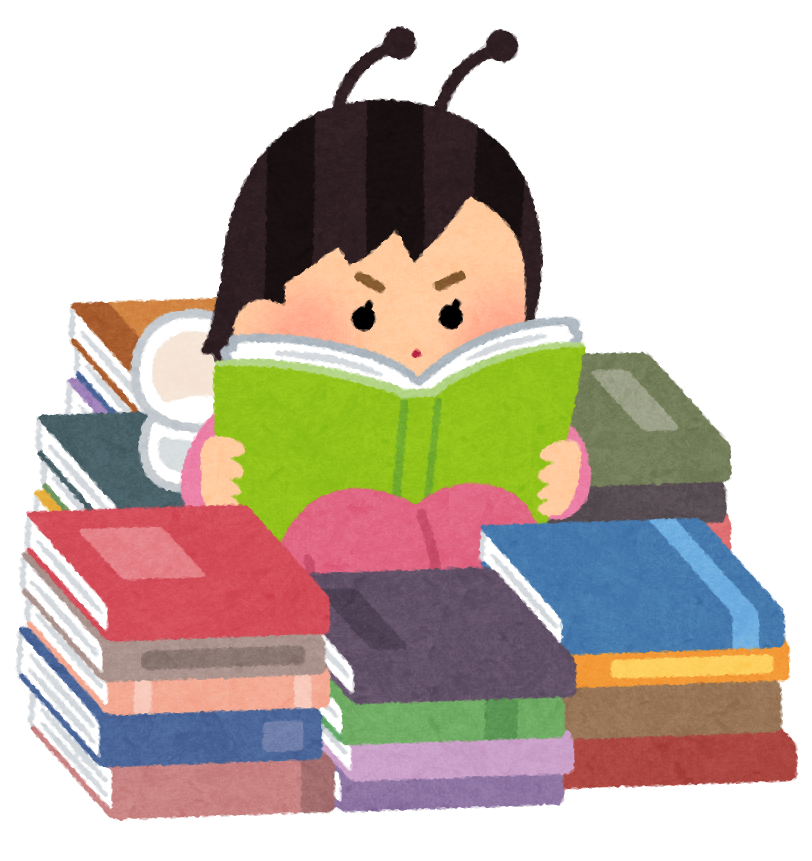 60 産業
60 産業  30 社会科学
30 社会科学  30 社会科学
30 社会科学 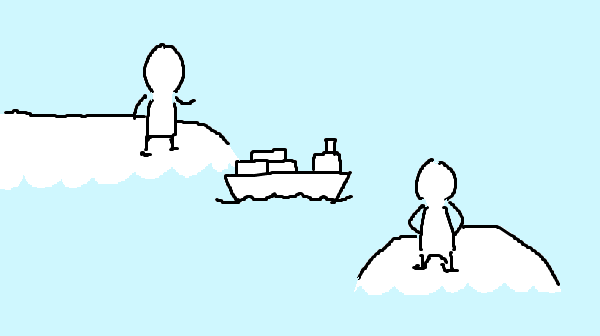 60 産業
60 産業 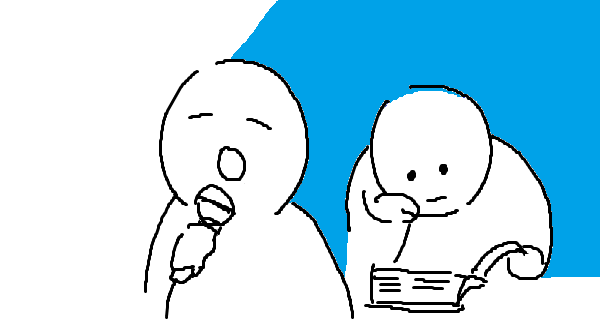 60 産業
60 産業