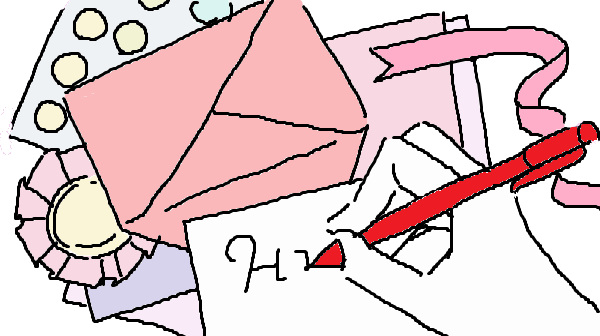 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学 『うれしいおくりもの』|イラストレーター・杉浦さやかさんのプレゼント
こんにちは。あさよるです。夏休みちょっとのんびりできる時間があったので、ここ数ヶ月分の日記をまとめていました(それを「日記」と呼ぶのかは定かではないが)。 いつも日記づくりのモチベーションになるのは、杉浦さやかさんのイラスト本です。もともと...
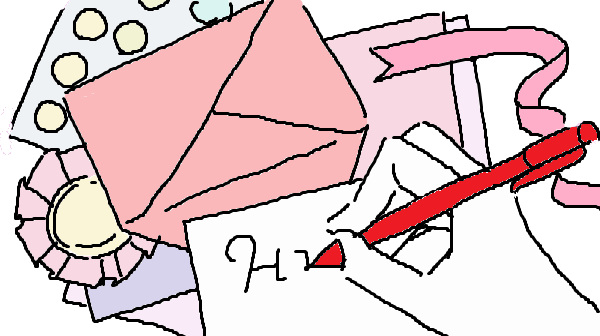 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学 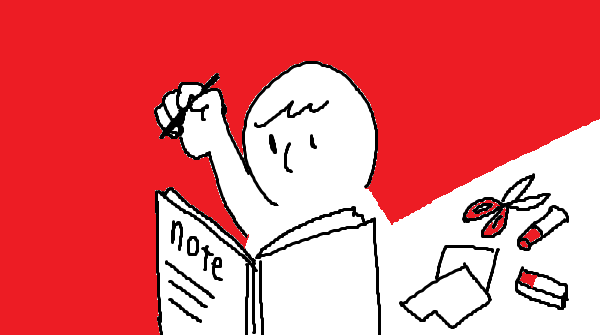 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学  59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学  59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学  59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学