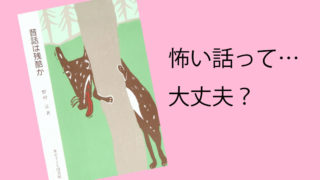 30 社会科学
30 社会科学 残酷な昔話・怖い絵本、読み聞かせていい?
昔話やおとぎ話は時に残酷な表現が含まれています。残酷はおとぎ話を子どもに読ませるのは悪いこと? 文芸学・民俗学・心理学の立場から残酷なおとぎ話を分析した書籍を紹介します。
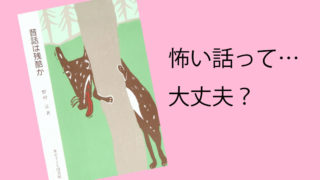 30 社会科学
30 社会科学 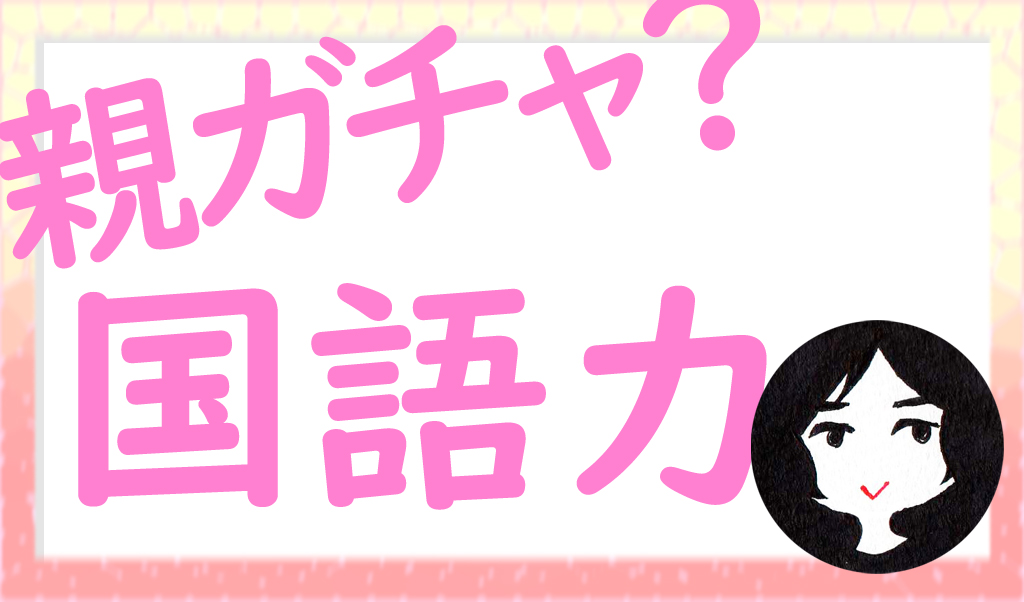 30 社会科学
30 社会科学 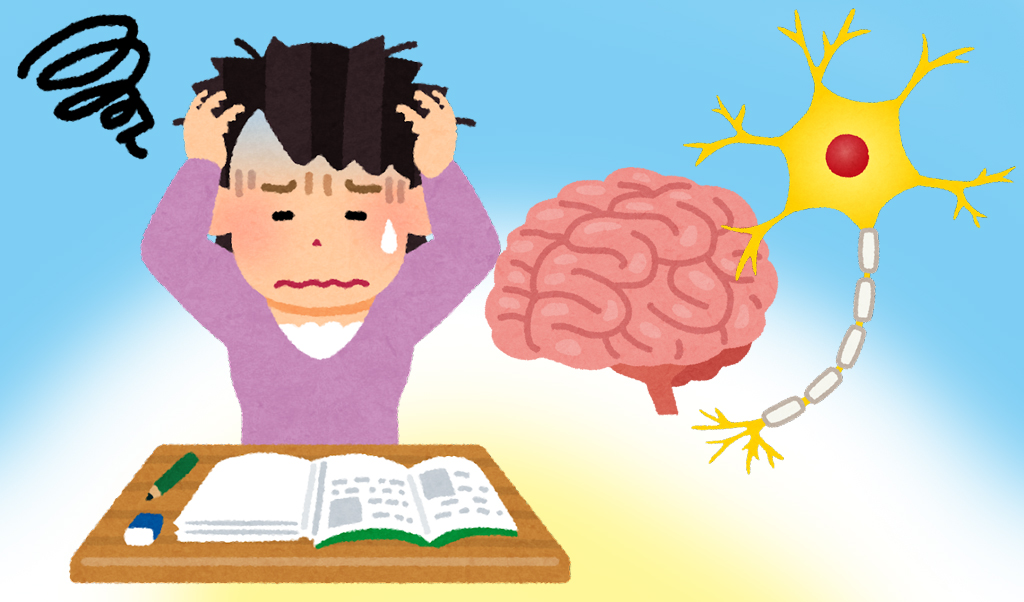 30 社会科学
30 社会科学  10 哲学
10 哲学  30 社会科学
30 社会科学