 30 社会科学
30 社会科学 『人は見た目が9割』|言葉は7%しか伝わらない
こんにちは。あさよるです。長年ヘアカラーをしていたんですが、数年前にカラーをやめて黒い髪にしたところ、しばらくやたらと人に絡まれる機会が増えて困っていた。明るい色に染めていた頃はそんなことなかったのに、「髪色が変わると世界が変わるのか」とな...
 30 社会科学
30 社会科学  10 哲学
10 哲学  コミュニケーション
コミュニケーション  10 哲学
10 哲学 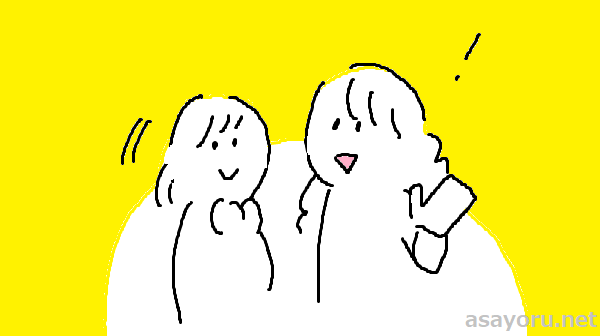 コミュニケーション
コミュニケーション