 20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史 【内容/レビュー】歴史を紐解くこと―「日本史を暴く」
「歴史の発見」というのは、こうやってなされるのか! 歴史学者の磯田道史さんは、今日も日本中の古書店で古文書を漁り読み解いてゆく。 歴史とは、地道な作業で解明されていくのだな。 中公新書の『歴史を暴く』おもしろい! 磯田道史さんによる歴史の語...
 20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史 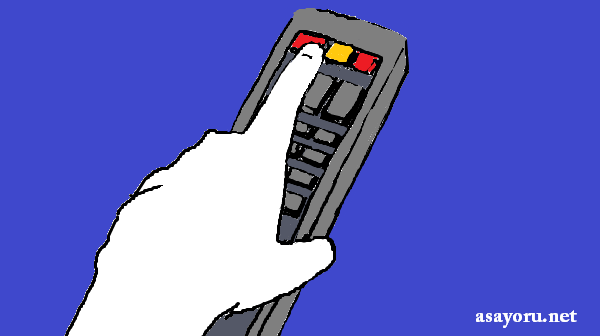 20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史  20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史  20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史  20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史