 10 哲学
10 哲学 『フランス人は10着しか服を持たない』|異文化の中でメンターに出会う
こんにちは。あさよるです。年末、大掃除がそろそろ話題になりはじめていて、片付けや掃除なんかの本を読みたいモード。今日読んだ『フランス人は10着しか服を持たない』は、人からすすめられた本でもある。しかも、外出先で本を読んでいたら初対面の人に話...
 10 哲学
10 哲学  10 哲学
10 哲学 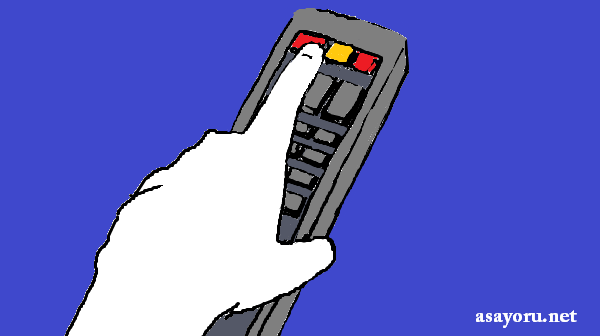 20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史  20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史  やる気の出る本
やる気の出る本