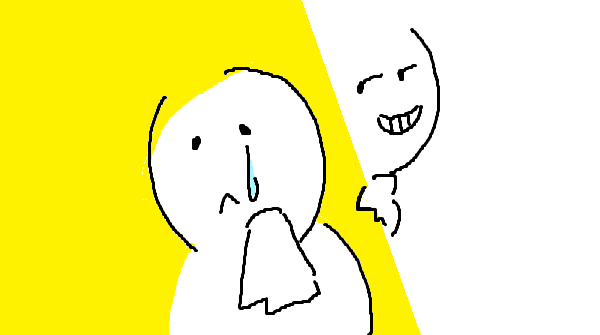 10 哲学
10 哲学 中野信子『シャーデンフロイデ』|ざまあみろ!人の不幸が嬉しい気持ち
こんにちは。えらそうばってる人を見ると、いじわるしたくなる あさよるです。自分のことを大きく見せようとしたり、上から目線な応対をする人を見ると、なんかこっちもトゲトゲした気持ちになっちゃう。ただ、相手の挑発に乗るのは、相手の思うつぼだったり...
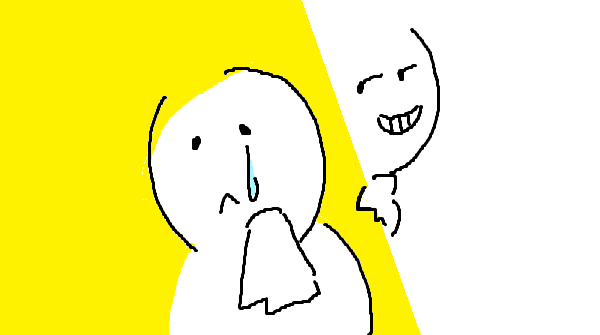 10 哲学
10 哲学 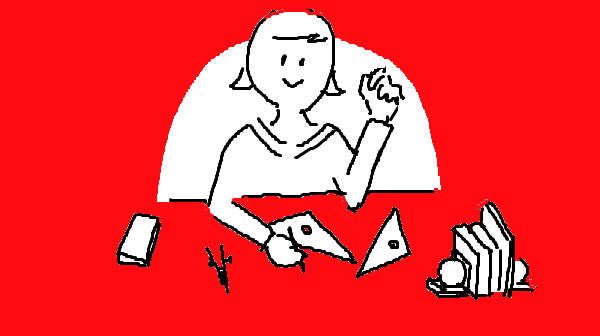 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学 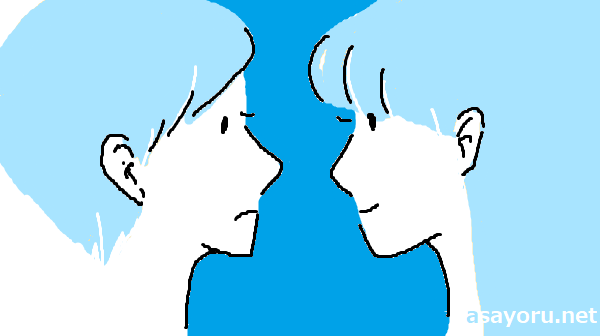 10 哲学
10 哲学  40 自然科学
40 自然科学 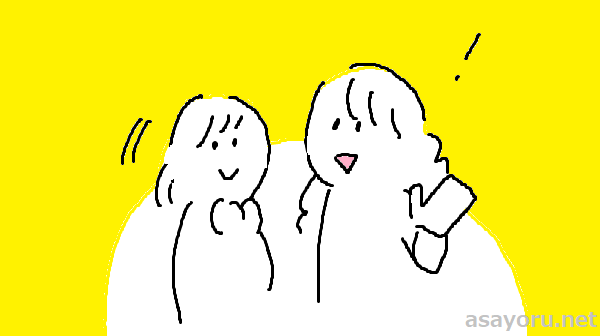 コミュニケーション
コミュニケーション