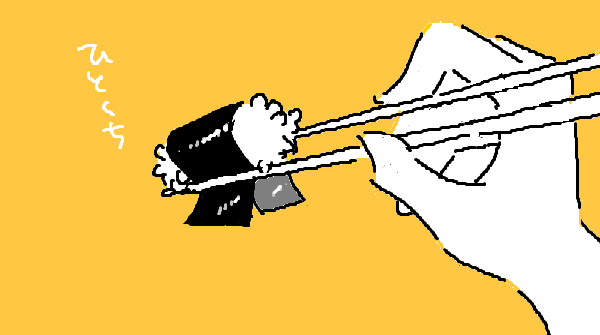 ダイエット
ダイエット 『10キロやせて永久キープするダイエット』|知性で攻略
こんにちは。お正月以来順調に増量中の あさよるです。普段わたし、そんなに量をたくさん食べるタイプではないんだけど(ちびちび小分けにして食べすぎるタイプ…)、お正月はあり得ないくらい量を食べた。普段食べない食材が待ち構えているし、仕事も休みで...
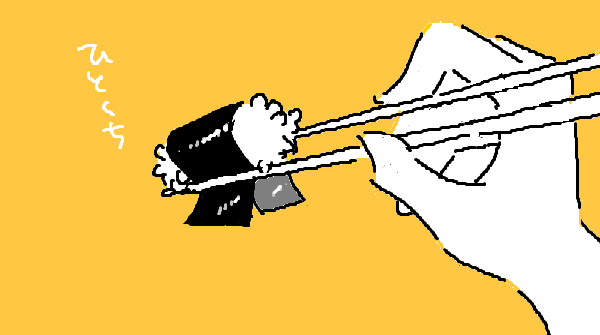 ダイエット
ダイエット  59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学  40 自然科学
40 自然科学 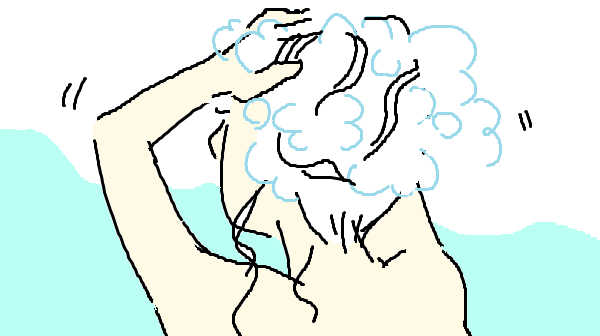 仕事に役立つ本
仕事に役立つ本 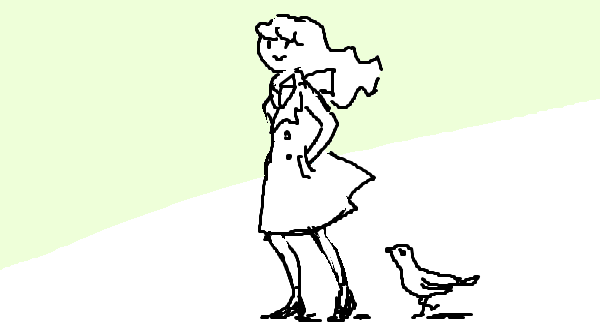 美容と健康
美容と健康