 読書記録
読書記録 『大人の教養としてのアート入門』|世界のビジネスマンの常識!リスキリングに
こんにちは。新型コロナの影響で、外出もできなにもず、この機会に読書を通して教養を身に着けたいと思われている方も多いと思います。今回はそんなズバリなタイトルの本を手に取ってみました。 どうせ時間をつぶすなら、自分のためになる時間を過ごしたいで...
 読書記録
読書記録  30 社会科学
30 社会科学 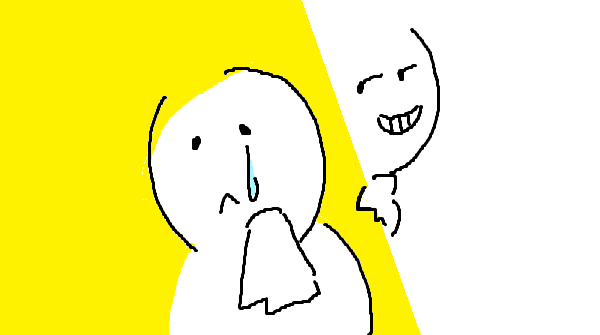 10 哲学
10 哲学 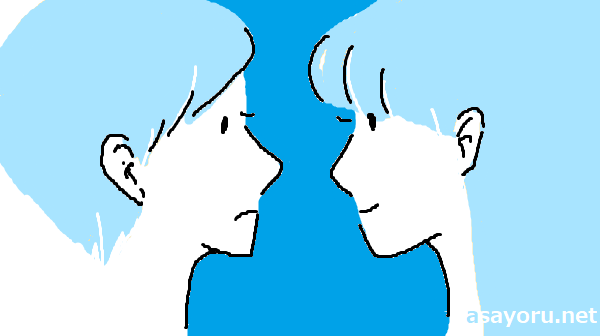 10 哲学
10 哲学  40 自然科学
40 自然科学