 20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史 『交雑する人類』|サピエンスの歴史…ルーツは「混ざり合い」
2018年、遺伝学者のデイヴィッド・ライクさんが、地球上の人類の交雑の歴史を太古の昔から紐解いてゆく。現在、グローバリゼーションの時代が到来し、人々はワールドワイドに行き交うようになったけれども、人々の大移動はなにも最近始まったものじゃない...
 20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史  40 自然科学
40 自然科学 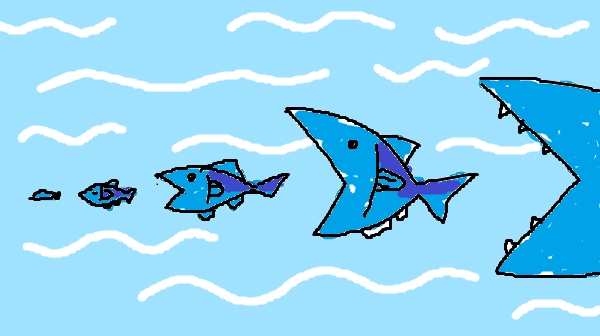 40 自然科学
40 自然科学 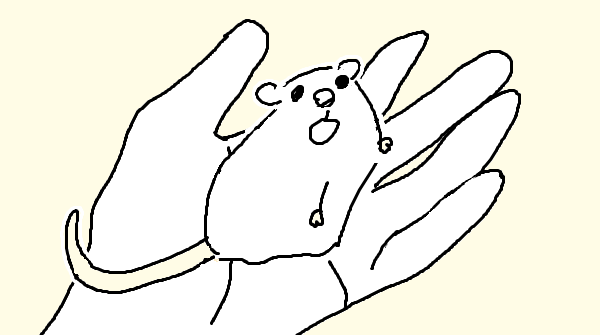 40 自然科学
40 自然科学 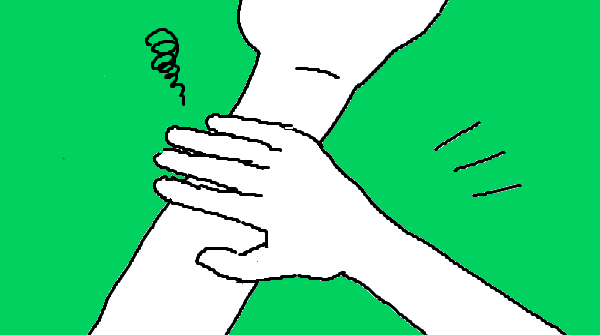 40 自然科学
40 自然科学