 50 技術、工学
50 技術、工学 『ゆる美容事典』|頑張り!より、ゆるっと習慣
こんにちは。あさよるです。お正月気分はさすがに抜けましたが、増えた体重と、サボっていたスキンケア、ヘアケアの影響がじわじわ出てきています。この季節、乾燥してイヤね。カサカサ感は絶対イヤなんだけど、どんどんカサカサになってゆく……( ノД`)...
 50 技術、工学
50 技術、工学  10 哲学
10 哲学  30 社会科学
30 社会科学  10 哲学
10 哲学 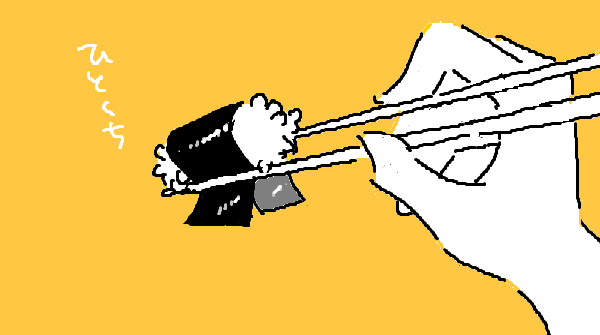 ダイエット
ダイエット