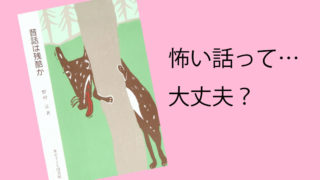 30 社会科学
30 社会科学 残酷な昔話・怖い絵本、読み聞かせていい?
読み聞かせする絵本は、大人が選んであげるのがほとんどだと思います。 そのとき気になるのはお話の内容。 昔話の中に残酷で怖い表現のあるお話があります。 たとえば、「赤ずきんちゃん」や「七ひきの仔やぎ」では、オオカミが赤ずきんややぎたちを食べて...
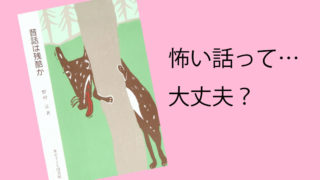 30 社会科学
30 社会科学  やる気の出る本
やる気の出る本  00 総記
00 総記 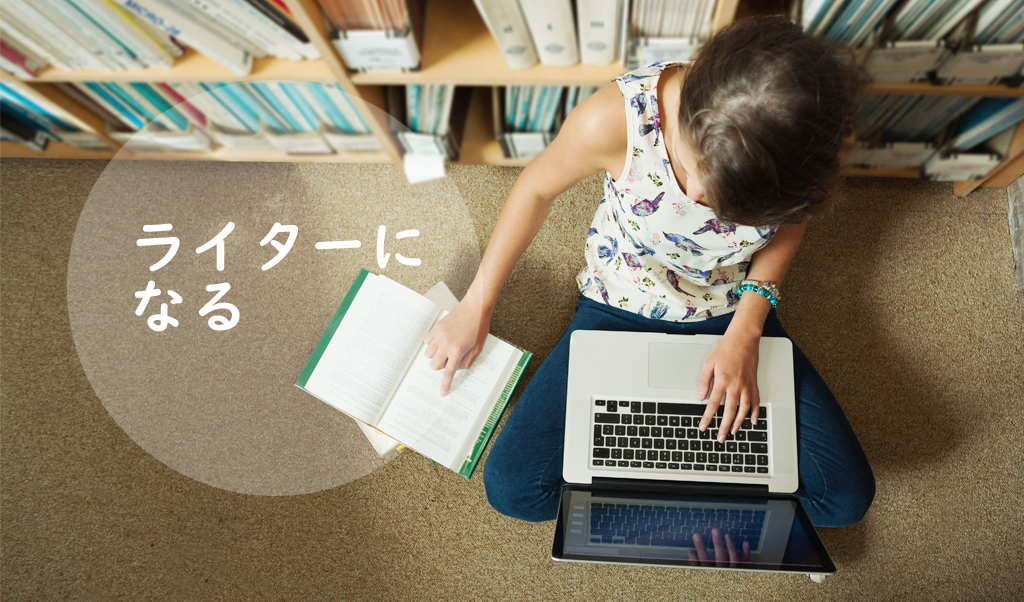 70 芸術、美術
70 芸術、美術  30 社会科学
30 社会科学