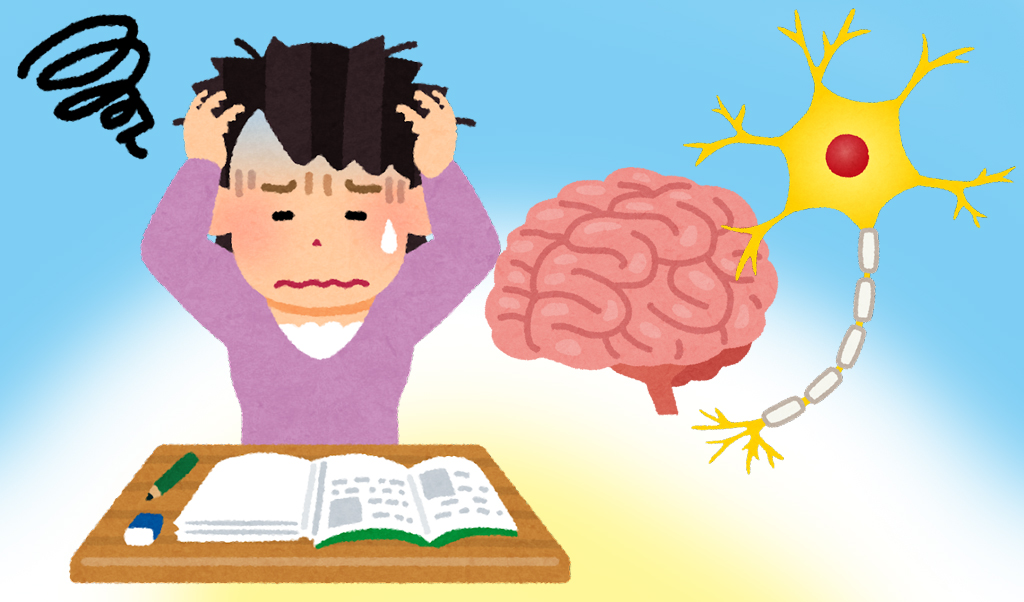 30 社会科学
30 社会科学 年代別勉強法をハックせよ! 年を取ると勉強できない…これマジ?
「勉強は若い内にしないとね。年を取るとできないから」 そんな言葉をかけられたことありませんか? あるいは、そんな言葉を“若い人”にかけていませんか? どうやらそれは間違いなようなのです。 勉強はいつでもできるし、むしろ年を取ってからの方が本...
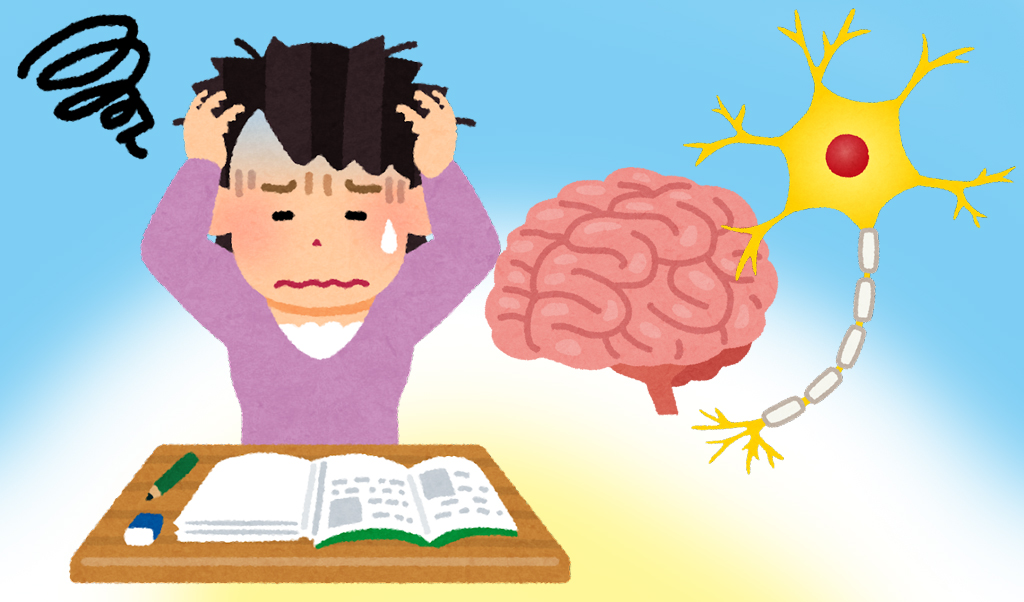 30 社会科学
30 社会科学  勉強法
勉強法  勉強法
勉強法  仕事に役立つ本
仕事に役立つ本  00 総記
00 総記