こんにちは。あさよるです。毎日本を読んではブログに書いても、読む本はなくならないし、自分が賢くなった気もしないので、人類の知識の貯蔵はすごいなあと思うし(日本語で書かれている本の量と分野の幅広さもすごい)、自分の浅はかさもすごいなあと思います(;’∀’)>
今回手に取ったのは『あなたの勉強法はどこがいけないのか?』。タイトルはドキッとせざるを得ません。
覚えることと、覚えないこと
『あなたの勉強法はどこがいけないのか?』では、中高生を対象に、勉強の心得、勉強との向き合い方について指南されます。
印象的なのは、勉強には「暗記しなくてもいいこと」と「覚えた方がいいこと」があるということ。暗記しなくても、頭で考えると筋道が見えてくるのは数学の公式です。本書では面積の求め方が例に挙げられていました。形が複雑な図形も、視点を変えると単純な計算で答えが求められる場合が多いのです。「考えることで大まかな筋道が見える」「およその答えがわかる」という感じでしょうか。数学は、暗記の量は少なく抑えることができます。
反対に、覚えた方がいい「暗記」の鉄則。脈略もない組み合わせの言葉を記憶するのは至難の業です。なので、暗記するものは「なるべく多くの情報を一緒に覚える」と、記憶に残りやすいのです。例を挙げると、
① 太った男が 錠を買った
② 力の強い男が ペンキのハケを買った
③ 眠い男が 水差しを持っていたp.50-51
上記の文は、要素は少なく単純ですが、脈絡がないので覚えるのは面倒です。しかし、情報量が増えると、一気に記憶に残りやすくなります。
①肥った男が買った錠は、冷蔵庫にかけるためです。つい冷蔵庫を開けて食べてしまうので、食べ物を出すのにわざと手間のかかるように、錠を買ったのです。
②力が強い男は、ウエイトトレーニングに使うバーベルにペンキを塗り、その後始末でハケを洗っていたのです。
③眠い男は、眠気覚ましにコーヒーを飲もうと考えました。そして、コーヒーメーカーに水を入れようとして、水差しを持っていたのです。p.52
こうやって文にすると、情報量は多くなり暗記量は増えているハズなのに、記憶しやすいんです。「この人はなぜこうしているのか」と状況を想像することにより、人と行為が結びついてすんなりと頭に入ってきます。思い起こすのも簡単です。暗記勝負になるとつい「覚えることは少ない方がいい」と考えてしまいがちですが、反対に覚える情報を増やす方が簡単です。歴史の年号を語呂合わせで覚えるよりも、「なぜどんな流れでそうなったのか」と他の情報と合わせて覚えるほうが思い出すのも簡単です。
さらに忘れてはならないのは、総合的な知識です。先ほどの例だと、③の「眠い男は、眠気覚ましにコーヒーを飲もうとした」という文は、「コーヒーは眠気覚ましになる」という知識があって初めて理解できることです。知識は総合的に、他の分野を行ったり来たりしながら、教養を深めてゆくことが、勉強を効率的にするのです。
「わからない」に注目する
本書後半は、本当はよくわからないのに、なんとなくわかった気になっている落とし穴に注目します。たとえば「蜘蛛は昆虫ですか?」と質問すると、学生たちは「蜘蛛は昆虫ではなく虫だ」と答ますし、昆虫の定義を言います。しかし定義を知識として知らなくても、昆虫の体の仕組みを知っていると、昆虫と虫の違いがわかるんだそうです。これも「教養」があれば、定義の暗記がなくとも、答えが導き出される例です。
こういう「わかったつもり」はたくさんあります。例として三好達治の詩「こんこんこな雪ふる朝に」が紹介されています。この詩は、特に難しい言葉も使われていないので「わかる」んです。が、改めてその情景について質問されると、パッとイメージが広がります。つまり、サラッと読んで「わかったつもり」でいても、鮮明にイメージしないと詩に描かれている様子を理解したとは言い難いですよね。
「わかったつもり」は厄介です。もしかしたら「わからない」「苦手だ」「嫌い」よりもたちが悪いかもしれません。『あなたの勉強法はどこがいけないのか?』ではこの「わかったつもり」をあぶり出すよう指南されております(;’∀’)>
大人は「分かったつもり」か「知ったかぶり」
はてさて、本書『あなたの勉強法はどこがいけないのか?』を読むと、大人になるというのは「わかったつもり」ばかり増えて、さらに「知ったかぶり」も増えることなんだなあと痛感します。これは仕方がない側面も大きいと思うし、一概になにもかもが悪いとは思いません。自分の知らない話題が展開されていても、自分だけが「わかりません」と発言して全体の流れを妨げてしまうことを遠慮することもありますし……。しかし、一人の人間としては「知ったかぶりはなるべくしたくないなあ」と思うし、そして「ああ、また知ったかぶりをしてしまった」とヘコむこともあります。
昔、甥が幼稚園へ上がる前の頃、電車が好きで、路面電車を見に行きました。あさよるが「あの電車は道路の上を、自動車と一緒に走るんやで。信号が赤になったら車と一緒に止まるねん」と教えると、「コイツなんかアホなこと言うてる~!でっ、電車が信号で止まるワケないや~ん!ぷぷぷ~!」みたいな、まさにプケラ状態で、ホントにこんな感じで → m9(^Д ^) 指さして心の底から嘲笑うようにバカにされたんですよね~。だけど、いざ路面電車が動き出し、本当に道路の上を走り、本当に赤信号で停止している様子を見て大フィーバー! さっきまでの嘲笑いモードから一変、「見て!見て!電車がぁああ!」みたな大興奮でキャーキャー叫び声を上げていました。私は「だから言うたやん」と思いつつ、「この手のひら返しはマネできんな」と、子どものパワーに圧倒されました。
こんな風に自分の発言が全く否定されるような現実に直面したとき、大人はどうしてもなかなか発言を撤回できません。それは頑迷とも言えるし、「発言の一貫性を失ってしまう戸惑い」もあると思います。だけど、子どもはそんなの全く気にせず、盛大に、さっきと全然違うことをしまう。この子どもパワーは大人になると羨ましい限りです。
知ったかぶりはやめられなくとも……
あさよるは、「知ったかぶり」「前言撤回できない」のは大人の性だと思うので、それ自体は仕方ないと思うし、他人のそんな振る舞いもなるべく寛容でありたいです(なかなか難しいですが……)。
その代わりに、人前では偉そうに知ったかぶりしちゃったなら、その後プチ反省して、後々コッソリと自習する習慣は持っていたいと思っています。自戒しつつ、自習できればいいかななんて思います。大人になると、どんどん誰も何も教えてくれなくなるし、自分からも「教えて」って言いづらくなってゆくし、せめて「後から勉強しよう」って習慣だけは死守したい……。
もちろん、「知りません、教えてください」って素直に言える人を見ると「偉い人だなあ」と尊敬しかないし、「それに引き換えわたしは……」とヘコむばかり。(;´д`)トホホ
関連記事
勉強法の本
- 『速読勉強法』|参考書を自分専用カスタムで時短!何度も読もう
- 『人生を変えるメンターと出会う法』|弟子が見込んで「先生」をつくる
- 『あなたを天才にするスマートノート』|手取り足取りノート術
- 『乱読のセレンディピティ』|乱読で予想外の好奇心にであう!
- 『「脳を本気」にさせる究極の勉強法』|我慢、苦労は脳にいい?
- 『王様の勉強法』を読んだよ
- 『キミが勉強する理由』を読んだよ
- 『コツコツ勉強するコツ86』を読んだよ
- 『じぶんの学びの見つけ方』を読んだよ
- 『子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの?』ソボクなギモン
- 『不勉強が身にしみる 学力・思考力・社会力とは何か』
読書法の本
- 茂木健一郎『頭は「本の読み方」で磨かれる: 見えてくるものが変わる70冊』
- 『「読む」「書く」「考える」は5分でやりなさい!』
- ピンチな時ほど本が読めない!『読んだら忘れない読書術』
- 『本は10冊同時に読め!』|欲張り読書家になる!
- 『あなたを天才にするスマートノート』|手取り足取りノート術
あなたの勉強法はどこがいけないのか
目次情報
はじめに
第一章 「苦手」ということ
1 「できない」と「苦手」の違い
なぜ、このようなことから?/苦手とは?/やるとできる?/「できない」と恐怖心/「できない」と一般的な能力
2 「できない」理由を知る
「できない」状態とは?/公式以外の知識が必要/「考え方」と「知識」/応用とできない理由/苦手意識はこうして生まれる
3 できるのは「応用力」があるから?
「力」という言葉/生まれつきだと打つ手はない?/別の補助知識/外から見ると同じ
第二章 「得意」と「素質」
1 「得意」と「素質」の反映か?
「得意」と「質素」/「素質」があればうまくいく?/英語の学力の例/「得意」の袋小路
2 関連をつける取り組み
機械的暗記は楽?/関連をつける説明/既存知識の働き/関連をつける勉強法
3 「能力」と「素質」
隠れた能力がある?/そもそも能力とは?/素質×勉強が大切なわけ/ハードとソフトの関係/大人への道
第三章 公式はやたらにおぼえない――勉強のコツ①
1 公式はやたらにおぼえない
役に立ち方の違い/平行四辺形や台形の公式はいらない/三角形の面積に長方形の公式が使える/長方形の面積がすべての基本/できる学生は公式を暗記していない/公式の丸暗記は長持ちしない
2 わかり方は使え方
「割り算」は「分ける」ことではない/少数で割る/利率の考え方/打率の考え方
3 知識はつながり
かけ算の順序/かけ算の意味/かけ算と割り算は1あたり量が中心概念/1あたり量で文章問題を考える/文章題というもの/勉強のコツ/他の教材でも同じ
第四集 この知識のどこがいけないのか――勉強のコツ②
1 広がらない知識はここがいけない
昆虫に関する貧弱な知識/動物として昆虫を意識する/視点の広がり/昆虫であるための条件/どのように広がるのか/応用問題に挑戦/高気圧と低気圧
2 現実とつながらない知識はここがいけない
磁石は鉄を引きつける/知識を使えるように変える/現実とよりつながる/現実とよりつながる知識
3 わからなくならない知識はここがいけない
凸レンズの例/「わからない」は勉強のきっかけ/二種類のわからない/わからないことがいっぱい/わざと危険にさらす/わからなくなれるか
4 文章におけるわかったつもり
詩の例/わからなくなるために/もっとわからなくなるために
おわりに――教わるということ
先が不透明な時代/教わることのイメージ/知識は道具
西林 克彦(にしばやし・かつひこ)
1944年、台湾高雄市生まれ。東京工業大学大学院教育学研究科博士課程中退。現在、宮城教育大学教育学部教授。「知識のありよう」をベースに、学習や学習指導をより細かくに考えることを実践している。著書に、『間違いだらけの学習論』『「わかる」のしくみ』『親子でみるける「わかる」のしくみ(興編)』(以上、新曜社)、『わかったつもり』(光文社新書)などがある。





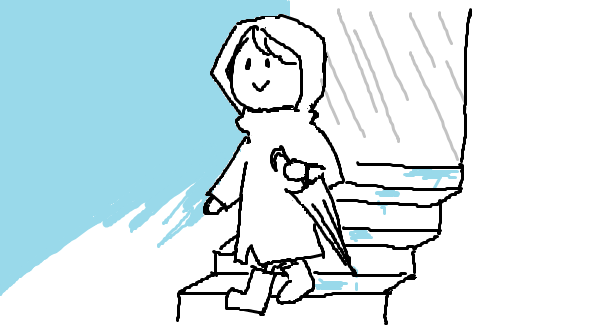
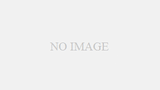
コメント
[…] 記事リンク:『あなたの勉強法はどこがいけないのか?』|知ったかより自習を […]