 10 哲学
10 哲学 池上彰『考える力がつく本』|絶対身につく力
こんにちは。あさよるです。わたしは社会人学生もやっているので、今は試験前で実は結構あたふたしています。 そうやって「自分は勉強している」と思っていたけれど、池上彰さんの『考える力がつく本』を読んで、他人の話をただ聞くだけ&読むだけでは、自分...
 10 哲学
10 哲学  仕事に役立つ本
仕事に役立つ本 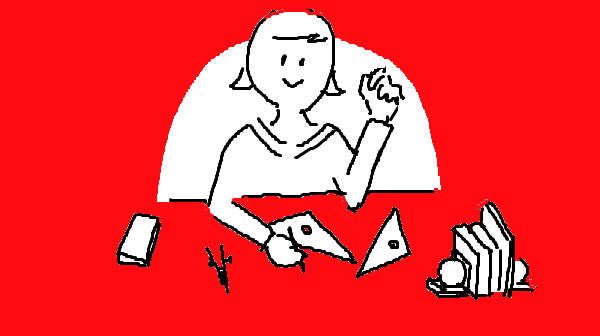 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学  コミュニケーション
コミュニケーション  10 哲学
10 哲学