こんにちは。あさよるです。『鬼速PDCA』は書店でめっちゃ平積みされてますね。 『鬼速PDCA』は書店でめっちゃ平積みされてますね。 話題本は追いかけるっきゃない精神でやっております<(_ _)>
PDCAサイクルを猛スピードで回すという、それだけの本だけど、話がシンプルだから話題になってるんじゃなかろうか。新人や学生にも向いているし、チームを動かす側の人にも使える。かなり幅広い層に役立つ内容だ。
問題を抱え込まない
PDCAサイクルはご存知のように、PLAN(計画)、DO(実行)、CHECK(検証)、ACTION(改善)の頭文字で、 P→D→C→A→P→D→C→A→P…と、グルグルと四つの手順を回してゆきながら、プロジェクトを進めてゆく。『鬼速PDCA』では、AはACTIONではなく、ADJUST(調整)が割り振られている。
「鬼速」というのは、PDCAサイクルをとても早く回してゆくことだ。著者の会社では、会議が週に1回ではなく、週に2回あるそうだ。そうすれば、社員が問題と出会っても、翌週まで持ち越さずに早く対応できる。これは、社員が問題を抱え込んだまま困り果ててしまう予防になる。だから、会議で問題を発表することがネガティブな評価に繋がってはいけない。むしろ、たくさん問題を見つけられることを評価するような環境づくりも大切だ。
『鬼速PDCA』は新人が読むことも前提とされており、初級者編から話は始まる。学生にも役立つだろう。多くの人が読んで、自分の業務や学習に当てはめられる。
自信・やる気に
PDCAのうち、PとDはやっても、C(検証)をしない人が多い。振り返りをせずに、やりっ放しで放置してしまうのだ。
検証するとき、できなかったこと、ダメだったことばかり挙げる人もいる。もちろん、マイナス点も冷静に受け止めなければならないけれども、うまくできたことや、よかったことも、同じように検証しないといけない。それは自分の自信になり、やる気につながる。
鬼速でPDCAは、問題を抱え込まず、どんどん計画→実行→検証→調整→計画…と回してゆくから、やればやるほど自信になり、やる気がでる。だから鬼速でやるのだ。
長い目で考える
PDCAサイクルが身につくと、大きなPDCA、小さなPDCAと、複数のPDCAサイクルを持てるようになる。それは中長期的な目標を持つことに繋がる。どうしても日々の業務に忙殺されていると、目の前の仕事でいっぱいになってしまって、中長期的な目標を考えられない。長い目で見ると役立つことであっても、それすら考えられなくなるのだ。例として、ブラインドタッチで高速タイプできるようになれば、一生能率が上がるのに、その訓練をする人は意外に少ないらしい。
大人も子どももPDCA
PDCAサイクルを鬼速で回したい人は、仕事人間だけではなく、趣味の多い人も同じだろう。むしろ、多趣味な人は多忙だから、タスクはさっさと終わらせて、次から次にやりたいことをやってゆく方がいい。
そう、PDCAサイクルは「仕事に使うもの」「管理職が使うもの」ではないのだ。プライベートを最大限充実させたい人にも鬼速PDCAはあてはまる。子どもも大人も関係ない。つまり、すべての人が持っていてもソンしない習慣だ。
みんなが知ってるようなことだからこそ、実直にやるかやらないかで、差が出ちゃうところなのかなぁなんて。わたしも趣味の計画を立てようかしら。
関連記事
- 『仮説思考』|行動が結果を、結果が経験を
- 『なぜ、あなたの仕事は終わらないのか』|夏休みの宿題はダッシュで終わらせる法則
- 『世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく』
- ハッピーエンドを手に入れる『エッセンシャル思考』を身につけよう
- 『最強の働き方』|ホントにすごいヤツはこんなヤツ!
- 『考える技術・書く技術』|説得力ある資料を作るには?
- 『超一流の雑談力』|当たり前だけど難しい「雑談力」!
- 稲盛和夫『生き方』|素朴な生き方だから、みんなが共感してしまう
- 『すごいメモ。』|今日のメモが、未来のアイデアをつくる
- メンタリストDaiGo『自分を操る超集中力』|誰でもできる。休憩と絞り込みが集中の鍛え方
- 『伝え方が9割』|人とのカンケイ、伝え方で変えられる!
- 『職場の問題地図』|仕事の問題を抱え込んでしまう人に
- 『嫌われる勇気』|やらないための“言い訳”を作ってた…だと?
- 「イシュー」を説明できますか?|『イシューからはじめよ』
- 『マッキンゼー流 入社1年目問題解決の教科書』|華やかな一瞬のために
- 『成長思考 心の壁を打ち破る7つのアクション』|低い目標を掲げろ!
- 「イシュー」を説明できますか?|『イシューからはじめよ』
鬼速PDCA
目次情報
はじめに
- 1章 前進するフレームワークとしてのPDCA
- 2章 計画初級編:ギャップから導き出される「計画」
- 3章 計画応用編:仮説の精度を上げる「因数分解」
- 4章 実行初級編:確実にやり遂げる「行動力」
- 5章 実行応用編:鬼速で動くための「タイムマネジメント」
- 6章 検証:正しい計画と実行の上に成り立つ「振り返り」
- 7章 調整」:検証結果を踏まえた「改善」と「伸長」
- 8章 チームで実践する鬼速PDCA
- おわりに
付録 鬼速PDCAツール
10分間PDCA記入例
富田 和成(とみた・かずまさ)
株式会社ZUU 代表取締役社長 兼 CEO
神奈川県出身。一橋大卒。大学在学中にIT分野にて起業。卒業後、野村證券にて数々の営業記録を樹立し、最年少で本社の超富裕層向けプライベートバンク部門に異動。その後、シンガポールでのビジネススクール留学を経て、タイにてASEAN地域の経営戦略を担当。2013年、「世界中の誰もが全力で夢に挑戦できる世界を創る」ことをミッションとして株式会社ZUUを設立。FinTech企業の一角として、月間250万人集める金融メディア「ZUU online」や、主要なピッチコンテストでも受賞歴のある投資家判断ツール「ZUU Signals」で注目を集める。これまでにシリコンバレーのベンチャーキャピタルを含む総額5.5億円の資金調達を行う。過去にGoogleやFacebookも受賞した世界で最も革新的なテクノロジーベンチャーアワード『Red Herring Asia Top 100 Winners』受賞。最近は金融機関のFinTech推進コンサルティングやデジタルマーケティング視線なども行い、リテール金融のIT化を推進している。著書に『大富豪が実践しているお金の哲学』(クロスメディア・パブリッシング)がる。




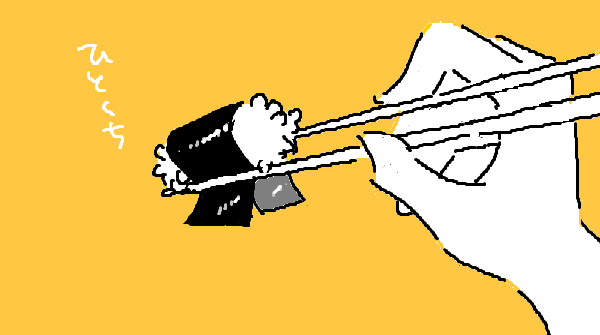
コメント