 30 社会科学
30 社会科学 ちきりん『マーケット感覚を身につけよう』|売れるところで売ろう
ちきりんさんはTwitterでもちょこちょこチェックしていて、新刊が出る度気になっている(今回読んだ『マーケット感覚を身につけよう』は2015年の本だけど)。とっつきやすくて誰にでもわかるように話が展開されていく、読みやすい本だ。だけど、書...
 30 社会科学
30 社会科学  10 哲学
10 哲学  10 哲学
10 哲学 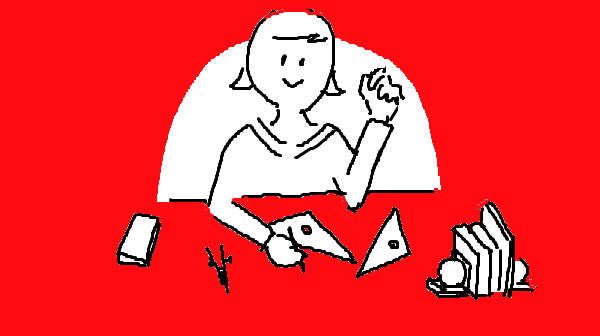 59 家政学、生活科学
59 家政学、生活科学  00 総記
00 総記