こんにちは。満員電車の中、奇跡的に座席に座りながら本書を読み通した あさよるです。『座らない』w
タイトルに惹かれて手に取ったのですが、結構真っすぐな“健康法”だなぁと感じました。
命を預ける相手に望むものは?
さて、自分の命を預ける相手。例えば医師とか、パイロットとか、運転手などですね。彼らに、何を望みますか?
例えば、夜更かしをして寝不足なままの医師に、手術を執刀されては困ります。パイロットや運転手だって充分に睡眠を取ってから是非とも出発していただきたい。睡眠不足って集中力を削ぎ、ミスの元ですからね。
では、自分が所属しているチームのリーダーにも、ある意味では命を預けているとも言えます。職がなくなると困りますからね。ということは、チームをまとめる立場にある人にも、十分な睡眠を望むべきです。睡眠不足で客観的判断ができず、ミスを多発させる人は仕事ができません。
もし、自分がチームを引っ張り、チームを動かす〈リーダーシップ〉のある人物ならば、今すぐ睡眠を十分に取り、健康体を維持する活動を始めましょう。本書『座らない!』は、ビジネスマンが健康習慣を維持するための本です。
『座らない!』?
で、本書タイトルは『座らない!』なのですが、読んでみると……あれ、座らない!要素なくない?という事実w
ちなみに、英語のタイトルは『EAT MOVE SLEEP How Small Choices Lead to Big Changes by TOM RATH』 。日本語でいえば「食べる 動く 寝る ちょっとの選択で大きな変化につながる」って感じ?
すごく普通ちゃあ普通のタイトルになっちゃうので『座らない!』って目を引く邦題になったのかな?と想像します。あさよるもそれに魅かれて手に取った口ですから、見事ひっかかってしまいましたw
食べる、動く、寝る
「食べる 動く 寝る」ってタイトルを〈普通〉を称しましたが、この普通で当たり前のことを徹底できている人がどれだけいるかってことです。
ちょっとした習慣、例えば友人と自宅で食事をするとき、ジャンクフードを選ばない。それだけで、食べ物が変わります。
睡眠が不足すると、昼間のパフォーマンスが1/3にまで落ちると言われています。自分では寝不足の害に気づいていなくても、周りの人は気づいている可能性があります。
運動すると脳機能が向上します。勉強したら運動を組み合わせましょう。記憶力も上がるようです。
当たり前と言えば当たり前。経験則で誰でも知っていそうなことです。しかし……繰り返しますが、「あなたはやっていますか?」ってところが重要です(苦笑)。ちなみに、あさよるは全くできていない……(;´Д`) ……ちなみのちなみに、昨夜はたぶん3時間も寝られなかったと思われ……(今もう、若干頭がグラグラしているw)
生活習慣が成果を変える
仕事ができるひと、優秀な人、成果が残せる人。彼らは、身体的能力が高いと考えてもいいのかもしれません。なぜ身体的能力が高いかという理由は、持って生まれた素質もあるでしょうが、ほとんどは日々の〈積み重ね〉なのでしょう。
あさよるは寝つきが悪い人なのですが、同じく寝つきが悪いと自覚している知人は、だから熟睡のために運動したり食事の時間をコントロールしたりと、気遣っていました。
ある人は、睡眠時間を長く確保したいからと、生活習慣そのものを見直す人もいます。
あさよるは……ですね(;´Д`)>トホホ
本書『座らない!』で紹介されている健康習慣って、ほんとちょっとしたことです。歩数を計るとか、座りっぱなしはやめてしっかり動く、とか、ほんと、あたり前のこと。
そのあたり前の健康習慣を手に入れるための30日プログラム。30日分のテーマが設けられ、一日に付き3つの習慣を実践します。
「これくらいならできそう」と希望が持てますし、また、「これ、やらなきゃマズいな」とも思います。
座らない!: 成果を出し続ける人の健康習慣
目次情報
本書を読む前に――「健康経営」が企業を変える
はじめにChapter01 三つの基本要素
カロリーよりも食事の質が大事
「座り続けること」が最大の敵
成果を出したかったらもっと寝るChapter02 小さな選択が大きな変化を生む
その一口で健康が決まる
座るのは禁煙より体に悪い
睡眠不足はあなたを別人にするChapter03 毎日正しい選択をする
炭水化物・タンパク質比率で選ぶ
家のなかの食べ物を配置換えする
歩きながら仕事をしてみるChapter04 よい習慣を築く
砂糖は老化を促進する
代替甘味料は解決策にならない
心と体のための20分ごとに2分歩くChapter05 自己免疫システム
表面の色で食べ物を判断する
風邪と睡眠の密接な関係
睡眠では質が量を凌駕するChapter06 生活習慣は遺伝子を上回る
新しい遺伝子を身にまとう
測定するだけで活動的になる
毎日8キロ歩くChapter07 もっと活力が出る生活をする
パンやライスを避ける
大皿料理で食べる量は10%増
運動後も脂肪は燃え続けるChapter08 タイミングが肝心
空腹時は悪食になる
早食いで肥満リスクは2倍
運動後は12時間気分が良いChapter09 応急処置
最初は注文が「アンカー」になる
身体の両側を使う
照明でメラトニンを調節するChapter10 賢い選択
タンパク質に優先順位を付ける
友人にジャンクフードをおごらない
短期的な目標を見いだすChapter11 健康的に仕事する
ウオーキングミーティングの効用
オフィス机での食事は危険
睡眠不足は泥酔状態と同じChapter12 きっぱり断ち切る
捨てた方がいい食べ物
友人のダイエットを手助けする
二度寝にはメリットがないChapter13 神話を打ち砕く
パンよりはバターよりはバターのほうが健康的
加工肉とジャガイモをやめる
寝室は冷やすChapter14 健康は自宅から始まる
お皿のサイズと色で痩せられる
自宅を中心に新しい習慣を築く
家族でしっかり眠るChapter15 早めに手を打つ
「おとり」に引っ掛からない
運動中の楽しさを思い出す
記憶するために眠るChapter16 しゃきっとする
高脂肪食は仕事の敵
学んだ後の運動で記憶が定着
規則的な運動は睡眠薬より効果的Chapter17 期待に沿う
食欲を削ぐあだ名を付ける
有機栽培は健康を意味しない
目標を周りに公言するChapter18 良い夜を過ごす
朝は豪華に、夜は簡素に
テレビ視聴は寿命を縮める
就寝前の1時間を聖域にするChapter19 物事をとらえ直す
ドライフルーツは果物ではない
商品名はパッケージにだまされない
眠るときは雑音を流すChapter20 日々のルーティンを調整する
加熱法が食べ物の良しあしを決める
長距離勤務は離婚への道
サマータイムで寿命が縮むChapter21 今を生きる
「腐るスピード」で食材を判断する
スマホ姿勢は体に負担
ストレスは睡眠を台無しにするChapter22 究極の老化防止法
トマトで「食事焼け」しよう
一歩ごとに若返る
睡眠があなたの見た目を決めるChapter23 健康的に意思決定する
健康的なものから食べる
人間は実は「運動中毒」
レム睡眠はストレスを軽減するChapter24 自己責任
お菓子は一握りにとどめる
1日5分だけでも外に出る
続けるために背中を押してもらうChapter25 予防策
減量でがんを撃退する
必要なのは運動の処方箋
二つの数字を暗記するChapter26 道を切り開く
お店で正しい食材を選ぶ
運動で脳と腸をきれいにする
一晩眠るだけで正しい判断ができるChapter27 新しい習慣を身に付ける
ケーキの代わりにベリーを食べる
ご褒美はほどほどにして楽しむ
毎日の行動の運動効果を知るChapter28 新しいトレンドをつくる
ブロッコリーは新しい流行
コーヒー、お茶、水にこだわる
ネクタイとハイヒールをやめるChapter29 すべてはつながっている
自分特有の健康リスクと闘う
減量すれば安眠できる
理想の睡眠は8時間Chapter30 まとめ
ほんの一口を侮らない
運動を習慣化する
睡眠は未来への投資おわりに
行動を起こす――新アプリ「ウェルビー」
著者あとがき
訳者あとがき
参考文献
トム・ラス[Tom Rath]
ビジネス・健康・経済の分野で活躍する人間行動学の専門家。「同世代の中でも最も偉大な思想家・ノンフィクションライターの一人」といわれる。過去10年で国際的なベストセラーを5冊執筆。処女作『心のなかの幸福のバケツ』(日本経済新聞社)は米ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー番付の1位、2013、14年には日本で未訳の『ストレングス・リーダーシップ』(日本経済新聞社)、『幸福の習慣』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、本書を合わせた5作の累計販売部数は600万部以上。
現在、研究や執筆、講演活動を精力的にこなす一方で、米ギャラップ社で上級科学者兼アドバイザーとして働く。同社では13年間にわたって「社員エンゲージメント・強み・指導力・ウェルビーイング」部門と統括。フォン・ヘッペル・リンドウ病研究所の副会長も務めた。ミシガン大学(学士)とペンシルバニア大学(修士)を卒業し、後者では現在非常勤講師。妻アシュリーと2人の子どもと共に、バージニア州アーリントンに在住。
牧野 洋(まきの・よう)
1960年生れ。慶応義塾大学経済学部卒、米コロンビア大学大学院ジャーナリズムスクール修了。日本経済新聞社でニューヨーク特派員や編集委員などを歴任し2007年に独立、執筆・翻訳活動に入る。2008~13年は在カリフォルニア、帰国後に早稲田大学ジャーナリズムスクール非常勤講師。著書に『官報複合体』(講談社)、『米ハフィントン・ポストの衝撃』(アスキー新書)、『不思議の国のM&A』(日本経済新聞出版社)、『最強の投資家バフェット』(日経ビジネス人文庫)、翻訳・解説に『知の巨人 ドラッカー自伝』(同上)などがある。



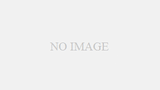
コメント