 30 社会科学
30 社会科学 副業から独立起業への道のり 第一歩は…
今すでに副業をしている方、これから副業をはじめようと考えている方は多いでしょう。 副業が解禁になった企業も増えています。 副業って、単にすきま時間でお小遣い稼ぎができるだけじゃないんです。 いつか諦めてしまった「夢」を叶えるために副業を始め...
 30 社会科学
30 社会科学 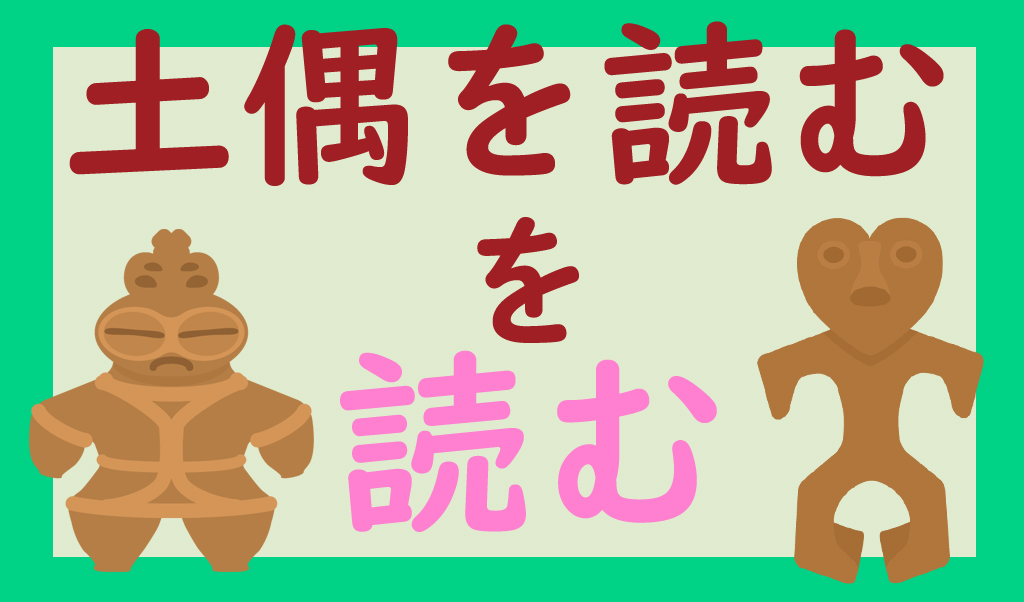 20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史  20 歴史、世界史、文化史
20 歴史、世界史、文化史 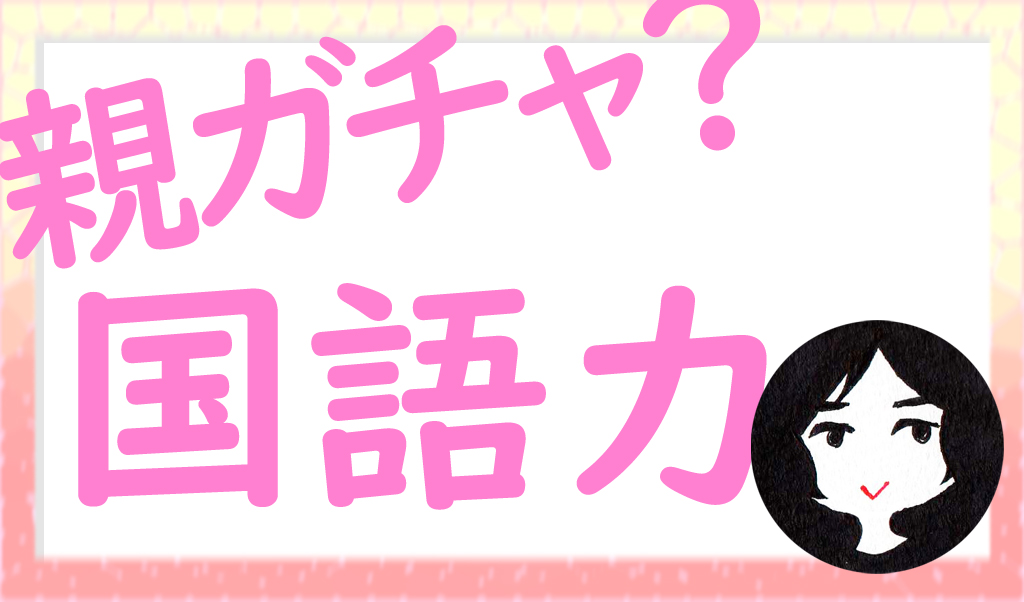 30 社会科学
30 社会科学 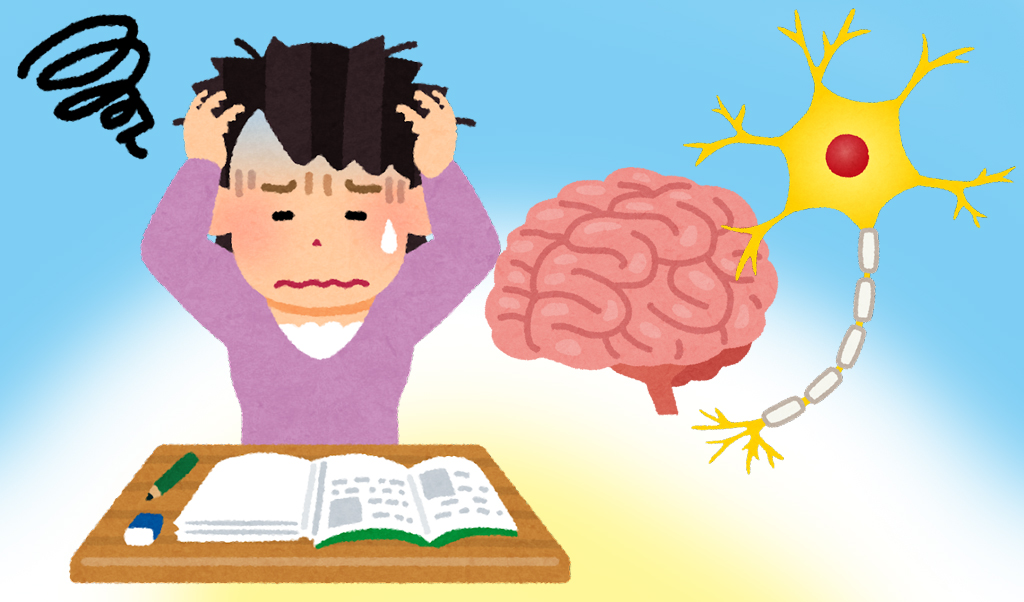 30 社会科学
30 社会科学