斎藤孝さんの本はつい読んでしまう。本書『1分で大切なことを伝える技術』も、内容もあまりチェックしないまま手に取ったのでありました。
1分で伝える。本書を読む前は、「せっかちな人が多いってことか?」なんて思っていたけれど、読了後は「手短に話を伝えられる力はとても大事だ」とえらく納得していたのです。
一分でコミュニケーション
本書『1分で大切なことを伝える技術』は、1分という限られた時間でプレゼンする大切さを解いている。特に訓練されていない人は、「5分で自分の考えを話してみて」と言われても、だいたいは制限時間をオーバーしてしまう。時間の感覚を常に意識して訓練し続けていないと、短時間で自分の考えを伝えるというのは難しいものだ。しかも本書では「1分」に考えをまとめるのだ。リアルに考えてみると、なかなか難問だろう。
一分というのは、ちょっと立ち話をしたり、相手を呼び止めて用件を伝えるような時間だ。その時間で「詳しいことはまた後日」なのか、同じ1分で「○○は△△で……」と伝えたい内容まで話せるのかで、コミュニケーションのスピードが格段に違う。
で、1分に考えをまとめる力って、会話だけではなく、たとえば「資料にまとめる」ことにも応用できるだろう。
「手短に話す」って、言葉で言うだけなら簡単で当たり前のことなんだけども、実際にできるようなになるならば、それはとても役立つし、大切な力なのだ。
褒める・叱る・励ます・謝る
もちろん1分で物事を伝える力は、仕事だけじゃなく私生活でも役立つ。コミュニケーションの存在しない場なんてないからね。
1分で手短に人を褒めたり励ませるならば、それは大きな信頼になるだろう。人を叱るのも難しいものだけど、1分で的確に叱れればモラハラの防止にもなるだろう。どうしても感情的になってしまいそうな場こそ、1分で伝える技術は必要なのかもしれない。
人に謝るときも、クドクドと長い話をしても、誰もいい思いをしない。やっぱりここでも的確な謝罪は大切だろう。
とうことで、コミュニケーション全般で「1分で伝える技術」は大切なのだ。
サッパリしてる方が濃密かも
わたし自身、人とのやりとりはなるべく端的な方がいいと思っている。ベタベタと長話をすれば親密になれるかと言えば、そうとは限らない。
それよりも、用件をパパっと伝えて、残りの時間はそれぞれの課題に思いっきり取り組んだ方が、お互いに良い時間を過ごせる。もちろん、人と一緒に過ごす時間だって、目の前のことに全力で集中した方が有意義だ。それはもちろん遊びも同じで、思いっきりのめり込んで遊んじゃった方が楽しいじゃない。
ということで、「1分で大切なことを伝える技術」はどんなシーンでも、誰との間でも役立つし、必要な力だと思う。
関連記事
- 『なぜ、あなたの仕事は終わらないのか』|夏休みの宿題はダッシュで終わらせる法則
- 『超一流の雑談力』|当たり前だけど難しい「雑談力」!
- 『世界の教養365』|今日のネタ帳はこれ
- 『すごいメモ。』|今日のメモが、未来のアイデアをつくる
- 『伝える力』|子どもへニュースを伝える力
齋藤孝さんの本
- 『三色ボールペン情報活用術』|読書しながらアウトプット
- 『読書力』|社会人力とは?教養とは?
- 『頭のよさはノートで決まる』|新しい自分のはじめかた
- 居心地の良い人間関係のために『雑談力が上がる話し方―30秒でうちとける会話のルール』
1分で大切なことを伝える技術
- 齋藤孝
- 2009/1/30
- PHP研究所
目次情報
- まえがき
- 第一章 「一分」の感覚をこう養え
- 第二章 万能! 川のフォーマット
- 第三章 一分間プレゼンテーション
- 第四章 コミュニケーションを学ぶための素材
- 第五章 実践! ケース別・一分の使い方
- 第六章 賞賛文化を根付かせよう~「褒める」「励ます」が日本を変える~
- あとがき――半紙が長いのはもはや環境問題だ
齋藤 孝(さいとう・たかし)
1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学大学院教育学研究科学校教育学専攻博士課程を経て、明治大学文学部教授。専攻は身体論、コミュニケーション論。
著書に『声に出して読みたい日本語』(草思社、毎日出版文化賞受賞、『身体感覚を取り戻す』(NHKブックス、新潮学芸賞受賞)、『「できる人」はどこが違うのか』(ちくま文庫)、『質問力』『段取り力』(以上、ちくま文庫)、『仕事力』(筑摩書房)、『コミュニケーション力』(岩波新書)、『齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ』(全13巻、PHP研究所)、『会議革命』(PHP文庫)、『ストレス知らずの対話術』『使える!『徒然草』』(以上、PHP新書)など多数。
小学生向けセミナー「斎藤メソッド」主宰







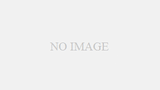
コメント
[…] 記事リンク:『1分で大切なことを伝える技術』|端的にコミュニケーション […]
[…] 『1分で大切なことを伝える技術』|端的にコミュニケーション […]