贅沢ってなんだろう?
贅沢をするために、「暇」を捨てたわたしたち。
山田登世子さんの本が読みたかった!
以前、山田登世子さんの『ファッションの技法』を読み、とても実りある書籍だったため、同著者の本を読んでみようと思いました。
本当は、ココ・シャネルについて書かれた本を読みたいなーと思いつつ、まずは先に入手できた『贅沢の条件』から読み始めました。
結論から言うと、あさよるは山田登世子さんのファンになってしまったのかもしれません(*´ω`*)
贅沢ってなんだろう?
あさよるは「贅沢がしたい!」と切に思うことが多々あります。たまには贅沢な食事がしたい!贅沢な旅行がしたい!贅沢なパジャマで寝たい!贅沢なインテリアに囲まれたい!
みなさんも同じような願望、あるんじゃないかと思います。
現代の我々にとって、「贅沢」って、物を買ったり旅行したり、いつもよりグレードの高いサービスを受けること。すなわち、贅沢をすることは、消費者として「消費」することです。
我々は消費をするために、せっせと働くのです。
「贅沢」の感覚は時代によって異なるのです。『贅沢の条件』では、フランス文化史を研究する著者が、主にヨーロッパでの「贅沢」をめぐる変遷を紹介されています。
絢爛豪華、きらびやかな男性たち
身分制社会では、男性がきらびやかな衣装で着飾り、ヒールを履き、宝石を身に着けていました。
17世紀のルイ十四世を招くため、財務長官は、絢爛豪華な城で祝宴を催します。そのたった一晩のパーティーのために食器や調度品が大量に用意され、王をもてなすのです。
ケタ外れな豪華さ、贅沢さですが、彼らにとって「贅沢」をすることそのものが仕事です。贅沢さは社会的立場を示しますし、浪費することこそが名誉。労働は不名誉なのです。
羨ましい話ですね(ヽ´ω`)
スーツ姿で闊歩する、ビジネスマンの時代
近代に入ると一転、ヒラヒラの豪華な服を着ていた男性たちは、ビジネススーツに身を包み、せっせと仕事に明け暮れます。
忙しいことがステイタスになり、暇を持て余すのは貧乏人の象徴。ビジネスマンたちはビッシリとつまったスケジュール帳を携え働くのです。
ビジネススーツからは彩色も削ぎ落とされ、機能性に特化しました。「労働は不名誉」とは正反対の思想です。
我々の生きる時代は「消費」が贅沢の象徴ですから、消費するための「報酬」の量がステイタスです。ですから、その報酬を得るための「労働」が贅沢への入り口なのです。
男性の分まで着飾る女性たち
男性が刺繍にまみれた衣装を脱ぎ捨て、ビジネススーツに身を包んだことで、その「装飾性」は女性の衣装に引き継がれます。
男性は自らの富を、引き連れる女性に豪華な衣装を着せることでアピールします。男性の分の装飾まで女性が追ったので、かつてないほどの豪華に豪華を極めた衣装が登場します。刺繍に刺繍を重ね、ビーズや宝石が散りばめられ、レースやギャザーをたっぷりよせ、それを重ね着します。
とても、そんな服装で女性は働けませんよね。
ココ・シャネル
ココ・シャネルという女性が、女性の衣装を一変させます。それは、女性の生き方、働き方の革命でした。
シャネルは豪華な衣服を脱ぎ捨て、色彩さえも剥ぎとった黒いスーツを身にまといます。質素なジャージー生地を縫製し、動きやすく働きやすい女性用スーツの登場です。
フェイクの宝石のアクセサリーを用い、かつての価値観を破壊しました。
あさよるはココ・シャネルという人物について何も知りませんでした。これから、シャネルについて知りたいと思いました。
「暇」は贅沢の敵になった
我々にとって、「暇」であることは忌まわしいことです。
週末に予定がなにもないこと、家に帰ってもすることがないことは、孤独や貧困を連想させます。
せっせとコンサートへでかけたり、ショッピングをしたり、部屋の中で読書をしたり、みっちりとスケジュールで詰まっています。
あさよるも、時間を持て余すとソワソワ落ち着かなく、「運動に」と散歩にでかけたり、料理や掃除を始めたり、「勉強だから」と本を開いたりします。移動中の時間ですら、何かしていないと気が済みません。
「暇」であることは贅沢なことのように思っていましたが、考えてみると、現代人にとって「暇」と「贅沢」は相反することなんですね。
暇=お金がない んですから、消費ができません。消費ができないと贅沢できないのです。
不要な「手間」こそが贅沢?
では、具体的になにを消費した時に「贅沢」なのでしょうか。
一つの答えとして、『贅沢の条件』では「手間」が挙げられていました。しかも、余計な手間。
スーパーへ行けば野菜が手に入るのに、あえて自分で野菜を育てる「手間」。新品で良い物はいくらでも手に入るのに、あえて古いものを探し、手に入れる「手間」。
「暇」「手間」……時間こそが現在の贅沢?
あえて手洗いが必要な生地を選んだり、現代では出汁を取るところから料理を始めることなんかも、贅沢かもしれませんね。
ああ、要するに「趣味」のカテゴリーに振り分けられるこだわりや美意識が「贅沢」なのでしょう。
「暇」「手間」……時間こそが贅沢?
「暇」が贅沢にしろ、「手間」が贅沢にしろ、そこに関与しているのは「時間」です。
有り余る時間をムダに過ごす「暇」に前時代の貴族たちは「贅沢」を見出しました。現代人は、時間をかけて「手間」かけることに「贅沢」を見出します。
もしかしたら、こんな「贅沢について考える」ことこそ、贅沢な時間の使い方かもしれませんね。
『贅沢の条件』では、贅沢な時間についても触れられます。それはそれは甘美な世界。あさよるには手に入らないだろう贅沢。
贅沢な時間のための、贅沢な知識
『贅沢の条件』を読んだからと言って、収入が上がったり、仕事の能率が上がるような内容ではありません。
贅沢の条件を知ったからと言って、贅沢ができるわけでもありません。しかし、「価値観」「美意識」を知ることは……うーん、知ったからと言って、どうなるものでもありませんね。
だけど、「贅沢」はそんな「ムダ」の中に宿るのは事実。生活を豊かにするのも、生きるに不要な、必要以上の知識や哲学だったりします。
万人にオススメ!とは言わないけれど、じっくりと自分の価値観を見つめたい人は、一読しても良いと思います。
関連記事
- 【要約】『「育ちがいい人」だけが知っていること』|育ちは変えられる
- 『フランス人は10着しか服を持たない』|異文化の中でメンターに出会う
- みんなと同じでいながら、みんなと違っていられる『ファッションの技法』
- 『極上の孤独』|「幸せ」も多様化している
- 『屋根ひとつ お茶一杯 魂を満たす小さな暮らし方』
贅沢の条件
- 山田登世子
- 講談社
- 1997/9/1
目次情報
はじめに――「豊かさ」と「幸福」と「贅沢」と
序章 贅沢の近代――「優雅な生活」
富裕層は贅沢か?/卓越化の表象/「暇なし生活」は贅沢の敵/閑暇という贅沢
1章 リュクスの劇場――きらびやかな男たち
1 ヴェルサイユという劇場
王の宝石/蕩尽の城/劇場としてのヴェルサイユ/「浪費」は名誉、「労働」は不名誉/王は踊る
2 ダンディズムの「喪の作業」
ヴェルサイユの黄昏/ダンディの「優雅な生活」/落日のメランコリー
2章 背広たちの葬列――ビジネス社会へ
1 タイム・イズ・マネー――産業社会の幕開け
「閑暇」は悪徳である/タイム・イズ・マネー/パリ地獄/ロビンソンたちの手帳
2 「富」 vs 「贅沢」
富と蓄積/wealth と luxe/フランスの国富/バブル都市パリ/ラグジュアリー・ブランド誕生
3 消費する女たち――有閑マダムの理論
男たちの葬列/女たちの「幸福」手帳/贅沢のプライベート化/「有閑階級の理論」
4 スーツを着る女たち
シャネル登場/装飾からの開放/スーツの越境/そして「有閑階級」はいなくなった……
3章 ラグジュアリーな女たち――さまざまな意匠
1 美の香り
◆ベルエポックの高級娼婦たち ◆サラ・ベルナール
2 贅沢貧乏
◆森茉莉 ◆与謝野晶子
3 趣味の貴婦人
◆白洲正子 ◆リタ・リディグ
4章 禁欲のパラドクス――修道院という場所から
1 ココ・シャネルの修道院
「土」の色/修道院のスペクタル/僧の水路/色のないステンドグラス
2 シャネルの贅沢革命
禁欲ファッションのルーツ/モダン・モード革命/「美」と「金」は別/ラグジュアリーのパラドクス/スーツを着た修道士
3 修道院の美酒
パンと葡萄酒/ベネディクト会からドミニコ会まで/シトー派のブルゴーニュ・ワイン/さまざまなる美酒
4 手仕事の贅沢さ
時間の贅沢/手作りの魂/贅沢は情報化できない/金を忘れた糸の美しさ
5 禁欲と楽園
ラグジュアリー修道院ホテル/アマルフィの楽園/プロヴァンスの「庭」/「農家」という贅沢
終章 贅沢の条件――時をとめる術
1 樹齢千年のオリーヴ
新しくない服/「古いもの」または伝統への欲望/ラ・ポーザ荘/樹齢千年のオリーヴ
2 はるかなもの
手仕事的時間/情報と物語/「退屈」という夢の鳥
あとがき
引用・参照文献一覧
図版出典一覧
山田 登世子(やまだ・とよこ)
福岡県生まれ
現在―愛知淑徳大学教授
専攻―フランス文学、文化史
著書―『メディア都市パリ』(ちくま学芸文庫)
『ブランドの世紀』(マガジンハウス)
『恍惚』(文藝春秋)
『晶子とシャネル』(勁草書房)
『モードの帝国』(ちくま学芸文庫)
『ブランドの条件』(岩波書店)ほか
訳書―バルザック『風俗研究』(藤原書店)
ポール・モラン『シャネル――人生を語る』(中央文庫)ほか



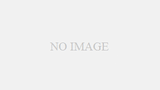
コメント
[…] 消費のために忙しく働くわたしたちへ『贅沢の条件』 […]