領土・国民・主権が、国家の三要素です。
それぞれ国家の根幹ですから、問題を抱えている事柄でもあります。
「家族」は最小の社会の単位です。
最小の「家族」が集まり「地域」を作り、それらが集まって「都市」そして「国家」を形成します。
ですから、家族について考えることと、国家について考えることは、深く関連していると考えられます。
実際に、家族の介護問題や、子育て、就業の問題などは、現在の日本の国が抱えている問題でもあります。
国家の形を考えるときに、私たちの文化の持っている「家族の形」を掘り下げてゆくのも、良いかもしれません。
私の属している日本社会はどのようなものなのか。それは国際社会を考えることにも繋がりますし、自分という個人を考えることでもあります。
「都市とは何か」定義により古代国家誕生の時期が変わる
古代国家の成立を考えるとき、まずは「都市とは何か」を定義しないといけません。
今日読んだ『古代国家はいつ成立したか』では、著者は3つの「都市」の条件を挙げています。
- 首都の政治センター機能、宗教センター機能、経済センター機能を持っている
- 王や役人、神官や僧侶、手工業者、商人など農民意外の人がたくさん住んでいる
- 人口が増え自給自足ができなくなり、必要な物資を外部に依存する
これは研究者によって見解が別れるので、条件が変われば、日本に都市が登場した時代も変わります。
ですので、都市国家の登場が、3世紀~8世紀ごろと解釈に幅があります。
今年2016年は、「大化の改新」に注目して勉強しようかなぁと、個人的に考えています。
特に明確な目的もないので、あくまで趣味の活動です。
そのために、大化の改新前後の時代にも目を配るよう心がけています。
古墳の形や数、造られた場所のナゾ
古墳の形のバリエーションが気になりました。
大化の改新(乙巳の変)で滅ぼされた蘇我氏や、その縁者たちは、「方墳(ほうふん)」という四角い古墳を作ったようです。
有名な石舞台古墳も、方墳に盛った土が崩れ、中の石室が外に顕になったものです。蘇我馬子が埋葬されたと言われていますから、やはり蘇我氏。
「河内政権論」をご存知でしょうか。3~4世紀にかけて、奈良に大きな古墳が作られていたのに、5世紀になり急に、大阪の河内に巨大な古墳群が出現します。現在の大阪府堺市周辺の百舌鳥古墳群です。中でも大仙古墳(あるいは仁徳天皇陵)は、国内最大の古墳であり、世界最大級の人口建造物でもあります。
しかし、それだけ巨大な古墳を作るにしては、なぜ奈良ではなく大阪に作られたのでしょうか。理由は諸説あり、「河内政権論」の論争が続いています。
都は奈良にあり古墳が大阪に造られたのか、大阪で別の王が現れそちらに主権が移ったなどなど、考えられている理由はさまざまです。
歴史の中に見えるもの
私たちの持っている歴史・日本史は私たちのルーツであるとともに、国家にとっても重大なものです。
主権や今に繋がる国家がいつ誕生したのかによっては、現在の領土の範囲に問題が生じるでしょう。
また、私たちの社会の最小単位「家族」を考える助けになるでしょうし、それは現在の社会問題を考えることにもなるでしょう。
関連記事
- 『天災から日本史を読みなおす – 先人に学ぶ防災』を読んだよ
- 『龍の棲む日本』|国土をぐるっと囲む龍が守り、災いを呼ぶ
- 『阿修羅像のひみつ』|CTスキャンで3Dデータ化された阿修羅たち
- 『正倉院-歴史と宝物』を読んだよ
- 『水洗トイレは古代にもあった―トイレ考古学入門』を読んだよ
古代国家はいつ成立したか
- 著者:都出比呂志
- 発行所:株式会社 岩波書店
- 2011年8月19日
目次情報
- はじめに
- 第一章 弥生社会をどう見るか
- 1 環濠集落の時代
- 2 倭国の乱
- 3 前方後円墳の源流
- 第二章 卑弥呼とその時代
- 1 邪馬台国の登場
- 2 前方後円墳態勢の成立
- 3 三角縁神獣鏡の謎
- 第三章 巨大古墳の時代へ
- 1 東アジアの大変動
- 2 主張系譜の断絶と政変
- 第四章 権力の高まりと古墳の終焉
- 1 豪族の居館と民衆の村
- 2 支配組織の整備
- 3 前方後円墳の終焉
- 第五章 律令国家の完成へ
- 1 律令国家と都市
- 2 都市の発達
- 第六章 日本列島に国家はいつ成立したか
- 1 国家をめぐる議論
- 2 民族系生と国家
- あとがきに代えて
- 図版出典一覧
- 参考文献
- 遺跡名・古墳名索引
著者紹介
都出 比呂志(つで・ひろし)
1942年大坂市生まれ
1964年京都大学文学部卒業,68年同大学大学院文学研究科博士課程中退
専攻―考古学・比較考古学
現在―大阪大学名誉教授
著書―『日本農耕社会の成立過程』(岩波書店)
『王陵の考古学』(岩波新書)
『前方後円墳と社会』(塙書房)
『古墳時代の王と民衆』(編著,講談社)
『古代国家はこうして生まれた』(編著,角川書店)ほか
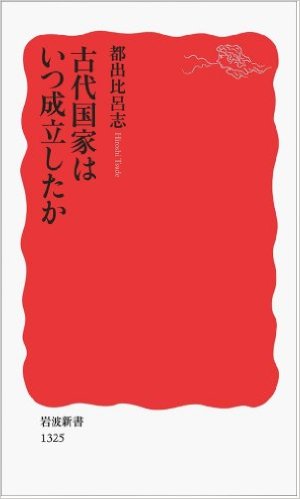

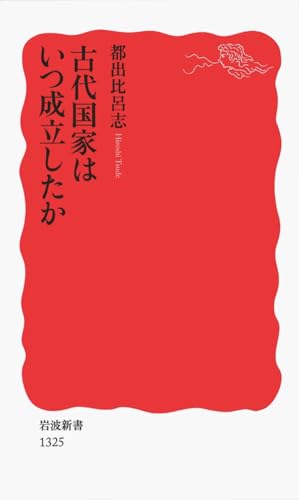
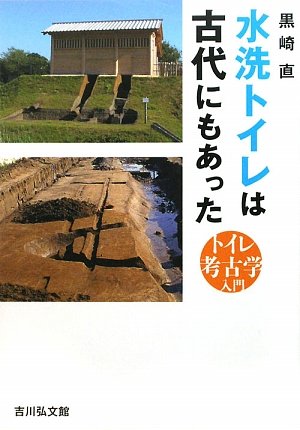
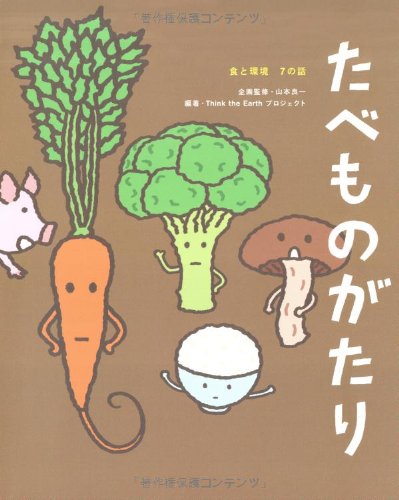
コメント
[…] 『古代国家はいつ成立したか』を読んだよ […]