「片足を突っ込む」「足を洗う」「足で稼ぐ」など、足を使った諺はたくさんあります。
「足掛け○年」という表現もあり、自分の意志のある行動を「足」に見ているのかもしれません。
値踏みされることを指す「足元を見る」という諺は、なんだか面白い表現です。
昔、駕籠かきは客の足元を見て料金を請求しました。
足が泥で汚れている人は、ここまでたくさん歩いて疲れているだろうから、少々高い料金でも籠に乗るだろう。
反対に、足元がまだ汚れていない人は、あまり疲れていないから、高いと籠を使わないだろう。
と、値踏みされるのです。
「足元を見る」とは、実際に足元を見られていたんですね。
現代でも、やはりそのままの意味でも、足元を人に見られているものです。
靴を見れば、その人がどんな人なのか、今日はどんな予定なのか予想ができます。
ビシッとオシャレに決めていても足元が子供っぽかったり、見るからにサイズの合っていない靴だったりすると、どんな印象になるでしょうか。
直立二足歩行をするために必要なこと
外反母趾や水虫、タコ、イボ、足の角質がカサカサになって荒れてしまったり…と、足のトラブルは次から次へやってきます。
ハイヒールやサンダル、冬にはブーツを履く女性は特に当てはまるかも知れません。
足のトラブルはそのまま歩行に直結します。
これまでにも何度か姿勢や歩行についての書籍を取り上げてきました。
『カラダが変わる!姿勢の科学』では、タイトルのまま、姿勢とは何か、立つとはどういうことかと科学的に解説がなされながら、正しい姿勢を作るための方法まで紹介されています。
正しい姿勢で歩行を行うと体への負担を軽減されるのですが、姿勢を保つためにはある程度の筋力が必要です。
そのためには正しく栄養を取り、体力維持をし続ける必要があります。
姿勢を見るだけで、栄養状態や体力作りや姿勢への意識の程度が分かってしまうということです。
足元を見られても、足元を見られないように整えておくには、姿勢、筋力、食事による栄養面と、生活そのものを正してゆかねばならないようです。
足元を見られないための足元のこと
『足もとのおしゃれケア』でも、姿勢や食べ物、飲み物、マッサージなどの体の手入れについて説明されています。
更にそれとともに、靴の手入れ方法も写真付きで紹介されています。
靴は消耗品だと履き潰したり、トレンドの靴を多少サイズが有っていなくても履いていたりと、靴の扱い方はそれぞれです。
本書では、サイズのぴったり合った靴や、オーダーメイドで作った靴を、しっかりメンテナンスをしながら大切に履き続けている方々が紹介されています。
足の先まで意志が行き届いているというのは、おしゃれのポイントかもしれません。
「二本の足で歩く」ということは、人が人たる所以でもあります。
靴は、二足歩行のための重要な役割を司っている道具です。
関連記事
- 『カラダが変わる! 姿勢の科学』を読んだよ
- 『フランス人は10着しか服を持たない』|異文化の中でメンターに出会う
- 『ニューヨークの美しい人をつくる「時間の使い方」』|みんなに親切に、自分を大切に生きる
- 『働く女性が知っておくべきビジネスファッションルール』|服が変われば収入UP!?
- 『ズボラ大人女子の週末セルフケア大全』|病気予備軍のオーガニック女子へ
Information
足もとのおしゃれとケア ~靴えらび・足の悩み・手入れのいろは
- 編集:COMODO編集部
- 発行所:技術評論社
- 2011年11月5日
目次情報
- Part 1. みんなの足元スタイル大集合 パンプスから登山靴まで10人の足もとおしゃれさん
- Part 2. 自分にぴったりな靴を見つける 靴えらび6のレッスン
- Part 3. 靴をもっと長く楽しむための手入れ 「履き方」「セルフメンテ」「収納」「リペア」
- Part 4. 冷えない、むくまない足もとでもっと健康に 健康な身体をつくる6のレッスン
- Part 5. 足の病気を知ろう よくある足のトラブルと健康な足をつくる5の手入れ
監修者プロフィール
代永 勉(よなが・つとむ)
靴修理工房「グルー」オーナー。広告デザイナーを経て靴職人に。埼玉川口ファーストステーションで靴修理職人として経験をつみ2009年独立。同年、目白にグルーをオープン。ブーツ、女性靴、スニーカーなど幅広い靴の修理に対応。オールソール、ヒール交換やカラーリングなどリメイクも手がける。客とのコミュニケーションを密にとりながら修理の相談にのる。
―COMODO編集部『足もとのしゃれとケア』(2011、技術評論社)p.159
長峯 由紀子(ながみね・ゆきこ)
長峯医院院長、医学博士。東京大学大学院終了。専門は形成外科、皮膚科、ペインクリニック科。日本形成外科学会正会員、日本皮膚科学会正会員、日本ペインクリニック学会認定医、日本麻酔学会専門医。1998年に長峯医院を開業。女性のための「足の専門外来」を開設。自身も足のトラブルを抱えていたが、セルフケアと独自の治療で克服した。その経験を活かし、女性のライフスタイルに合わせたきめ細やかな治療を実践している。
―COMODO編集部『足もとのしゃれとケア』(2011、技術評論社)p.159




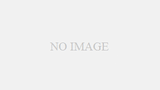

コメント
[…] 『足もとのおしゃれとケア ~靴えらび・足の悩み・手入れのいろは』を読んだよ […]