こんにちは。本を読むからブログを書くのか、ブログを書くから本を読むのか、そろそろ分からなくなっている あさよるです。
最近「本をたくさん読む」モードで稼働中です。読書をするにはまず、手元に本を用意しなければなりません。はてさて、読みたい本がたくさん溜まっているときは、それを消化してゆけば良いのですが、読み尽くしてしまったときなかなか困ります。
なんか、おすすめの本をリストアップしてくれている本がないかなぁと思いつめること多く、ある日バッタリと茂木健一郎先生の『頭は「本の読み方」で磨かれる』に出会いました(本の最後に、本書内で取りあげられた本のリストがあるのですv)。
本って、こうやって読む!
『頭は「本の読み方」で磨かれる』は「本をどう読めばよいのか」を知らせる指南書です。ですから、読者の対象は、普段本を読む習慣がない人 or 中学生や高校生向け。要するに「これから本を読むぞ!」って人向けです。
例えば「最初から最後まで読むのは大変だったら読みたいところだけ読んでもいいよ」とか「じっくり読んでもいいし、飛ばして読んでもいいよ」と助言します。そう「本をたくさん読む人って、見切りをつけるのも早い」と、あさよるも10代の頃アドバスをもらいました。
また読書を「かっこいい」という切り口で紹介されているのも、なんだかいいなぁとw というのも、あさよるが高校生の頃「ブンガクとか読むとかっこいいカモ」と思い、高校の図書室へ足繁く通った過去があったからです。
そして、『頭は「本の読み方」で磨かれる』では「乱読」が推奨されています。乱読とは、手当たり次第に本を読むことです。系統立った学習ではなく、目についたものすべてを飲み込み血肉にしてしまう。その「好奇心」こそが、頭脳を磨くことです。
もちろん、ジャンルをランダムに読むのですから、雑誌やマンガもどんどん読みます。「手当たり次第」ですから。
ターゲットは誰だ!?
本書『頭は「本の読み方」で磨かれる』の、難点があるとすれば、この本を読むのは誰だ?ということです。
本書のターゲットは「これから本を読むぞ!」って人向けですが、その人たちは『頭は「本の読み方」で磨かれる』を手にとるのか?と疑問に思うからです。初っ端に“本の読み方の本を読む”って起こるのかなぁ?
そして、普段から本を読む人たちにとって、本書で紹介されている内容は既に実践済みかも。だから真新しさは少ない?
間を取って「たまに本を読む」人が読むのでしょうか。
そこで あさよるが考えたのは、“読書の習慣がある人”が、“これから読書習慣を身に着けようと燃えている人を”に、投入する燃料ではないか?という仮説です。好奇心の世界をチラ見せして、さらに好奇心をあおる戦法!
茂木先生をお手本にさり気なくプレゼンしたら大丈夫!?
自分の読書体験にニンマリ
といいつつ、あさよるが本書『頭は「本の読み方」で磨かれる』を読んでも、とてもおもしろかったです。自らの読書経験と重なる部分もたくさんあり、また「あさよるはこう思う」と持論を打ち出してみたり、本と対話しているような読書でした。
幼い頃、夢中で読んだ本たちの存在を思い出し、「ああ、子供の頃からショーモナイ本ばっかり読んでたなぁ」と思い出し笑い。
あさよるはオカルトやオーパーツや世界七不思議なんかの「謎」の本を好んで読んでいました。先程“ショーモナイ”と書いてしまいましたが、それらのロマン溢れる眉唾話を熱心に読んでホントに良かったと思います。だって、ロマン!生きてゆくのにロマンは必要です。あさよるは今でも、それらの話を他人に教えようとしてしまいますw
そんな感じで、ご自身の読書経験と照らし合わせ、「だよね~」「読書ってこれだよね~」とアルバムをめくるように、自分の読書を振り返られる本です。
“そのひと言”を本にした本
この本のターゲットは誰だ?と書きましたが、読書家の方々が嬉しい内容ではないかなぁと思います。なぜなら、著者の茂木健一郎さん自身も読書家であり、なにより本を読むことを大切にしている人だからです。
「本を読むのを愛している」と書こうとしましたが照れくさいのでやめました。茂木健一郎さんだって、そのひと言を使わずに、その思いを一冊の本に書き出されたのではないでしょうか。
食べものが自分の身体を作るように、また書物も自分を作ります。それを改めて再確認する内容でした。なにより、自分のかつて読んだ本をたくさん思い出しました。それが一番うれしい経験でした。
関連記事
- 『バカにならない読書術』|本を読まない!身体を使え!
- 『王様の勉強法』を読んだよ
- 『「脳を本気」にさせる究極の勉強法』|我慢、苦労は脳にいい?
- 『仮説思考』|行動が結果を、結果が経験を
- 『「賢い子」に育てる究極のコツ』|脳の成長は〈ワクワク〉!
- 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』
頭は「本の読み方」で磨かれる 見えてくるものが変わる70冊
- 茂木健一郎
- 三笠書房
- 2015/6/24
目次情報
はじめに
本は、あなたを映す「鏡」である1 これが“自分の頭で考える力”をつける第一歩
本を読む人、読まない人、そこに圧倒的な差が生まれる頭がいい人は、どう本を読み、どう活かしているのか?
メリット1 読んだ本の数だけ、高いところから世界が見える
脳の側頭連合野にデータを蓄積する
読んで“巨人の肩”に乗る
「学び」とは「読むこと」だメリット2 脳を鍛えたいなら、読書がいちばん
なぜ、この一冊で脳が鍛えられるのか
「言葉の筋力」を磨く
まるで、ご飯つぶを噛むように
この方法で「ドーパミン」を出すメリット3 生きる上での「ワクチン」になる
メリット4 本を読むのは、シンプルに「かっこいい」
ファッションアイテムとして考える
こんな“見栄”なら張っていい
カバーをかけるのは日本人だけ2 こんな「教養のある人」こそが強い
仕事、人間関係、幸福……あらゆることは、読書に左右される「優等生」ではなく、「オタク」を目指す
情熱は、脳の“最強のエンジン”
「世界の広さがわかる人」は何を見ているか地頭のよさは、こうしてつくられる
「何がやりたい?」「ただひたすら本が読みたい」
「知的な付加価値をつくれる人」の頭の中
ちょっと「危ない人」になれ
3 「自分を成長させてくれる本」の見つけ方
「上質な文章」に触れることが、何よりも脳を鍛える文学界の教養王「夏目漱石」
漱石の“ダメ出し”を見抜く
ストーリーを現代の背景で読み解いてみるとまずはこれを読め――ジャンル別「チャンピオン」
なぜ、いい本は「会話のネタ」になるのか
ベストセラーは口コミによってつくられる
大事な情報収集は「弱いつながり」から雑談力の底力
人間だけが持っている「すごい能力」
世界一のコンピュータにも、絶対に真似できないこと
「本」を「語るもの」として読む
4 知識を吸収し、人生に活かす技法(スキル)
膨大なデータを血肉にする「7つの絶対ポイント」絶対ポイント1 脳には「雑食」がよい
「奇跡のリンゴ」が実るように
“UFO”も“物理”も両方学んでわかったこと
「すべてが正しい本」は存在しない
「マンガは子どもの脳によくない」は本当か絶対ポイント2 「複数」を「同時進行」で
絶対ポイント3 自分の軸となる「カノン」をつくる
ソクラテスのカノンは『イソップ物語』
絶対ポイント4 「事情通(オタク)」と仲よくなる
キーワードは「そうなんだ」
「ネタバレ上等」と心得る絶対ポイント5 「ネットの気軽さ」と「紙のプレミアム感」を使い分ける
なぜ、これほど「書店に行くこと」が重要なのか
電子書籍はどう使う?絶対ポイント6 「いい文章」「悪い文章」を知る
コピペな脳を劣化させるという事実
言葉にはこんな「経済価値」がある絶対ポイント7 “速読”を使いこなす
こんなときはサッと飛ばして、いさぎよく次に行く
5 「一生使える財産」としての厳選10冊
「知の宝庫」から、本当に必要なものを盗め!複雑な時代に立ち向かう――その“姿勢”
「国家」と「自分」を理解する――自由を考える一冊 『選択の自由』
「暗黒面」こそが人を輝かせる――「人間の土台」をつくる一冊 『悲劇の誕生』
明るいノーベル賞科学者――「理系思考」がわかる一冊 『ご冗談でしょう、ファインマンさん』
「本当のやさしさ」とは何か――「心の美」を見つける一冊 『硝子戸の中』
人間が神を見るとき――「宇宙と地球」を知る一冊 『宇宙からの帰還』
「今ここ」を懸命に生きる――「救い」を見出す一冊 『イワン・デニーソヴィチの一日』
“人の痛みがわかる人”とは――闇と対峙する一冊 『獄中記』
「カワイイ」はここから始まった――「日本の心」を学ぶ一冊 『枕草子』
固い頭を柔らかく――「考える力」を養う一冊 『ファウスト』本書で紹介した本のリスト
茂木 健一郎(もぎ・けんいちろう)
脳科学者。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程終了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て現職。「クオリア」(感覚を持つ質感)をキーワードとして脳と心の関係を研究している。ベストセラーとなった訳書『「脳にいいこと」だけをやりなさい!』『もっと「脳にいいこと」だけをやりなさい!確実に自分を変えていく法』(いずれも三笠書房)の他、『脳と仮想』(新潮社)『結果を出せる人になる!「すぐやる脳」のつくり方』(学研パブリッシング)など、著書多数。








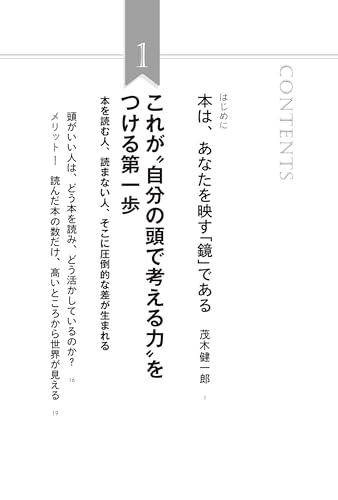









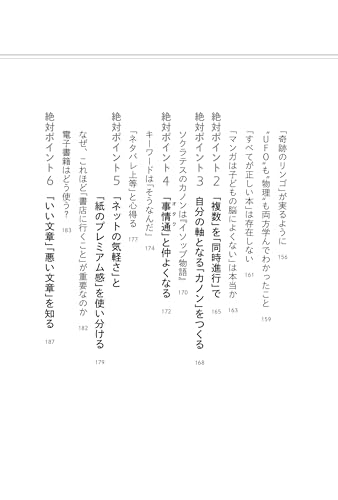


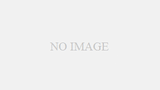
コメント
[…] 記事リンク:『頭は「本の読み方」で磨かれる: 見えてくるものが変わる70冊』 […]
[…] 『頭は「本の読み方」で磨かれる: 見えてくるものが変わる70冊』 […]
[…] 茂木健一郎『頭は「本の読み方」で磨かれる: 見えてくるものが変わる70冊』 […]
[…] 茂木健一郎『頭は「本の読み方」で磨かれる: 見えてくるものが変わる70冊』 […]
[…] 茂木健一郎『頭は「本の読み方」で磨かれる: 見えてくるものが変わる70冊』 […]
[…] 茂木健一郎『頭は「本の読み方」で磨かれる: 見えてくるものが変わる70冊』 […]