とりあえずジョギングしなさい!
だけど、それ、なんで?
筋トレの効果を知りたかった
軽い筋トレをしばらく続けて来ました。
「スロトレ」という、無酸素運動を用いたもの。スロトレは、週に数回、数分間のトレーニングで効果が得られる、面倒くさがり屋には丁度いいトレーニングでした(苦笑)。
運動やトレーニングについて、もっと知りたいと思うようになり『脳を鍛えるには運動しかない!』を読みました。
最近、なんでも「だいたいのことは腹筋でなんとかなる」なんて宣っていたので、タイトルがまさにピッタリ(笑)。
脳を鍛えるには「有酸素運動」しかない!
本書の結論から言いますと、「脳を鍛えるには有酸素運動しかない」!これに尽きます。
有酸素運動…ジョギングやウォーキングを30分、1時間と続けると体の血行がよくなり、体に良い。
体に良いことは、脳にも良いことです。脳も体の一部ですからね。
気分の落ち込み、脳のトラブルにはジョギングせよ
気分がなんだか落ち込むなぁという時、落ち込んでいるのは、気分ではなくて肉体だったりします。
肉体の状態によって、「気分」と呼ばれるものも変化します。「ダルい」のは気持ちではなく、体がダルいんですね。
新型うつや、パニック障害、不安障害にはジョギング
うつやパニック障害、不安障害も、有酸素運動が有効です。
上記のような症状には、運動をしたとき分泌される「乳酸」が、症状を悪くします。ですから、これまでうつやパニック、不安障害に運動は禁物でした。
しかし、『脳を鍛えるのは運動しかない』では、ここからさらに踏み込んだ実験結果が示されています。
不安障害を抱える人にジョギングをさせると、どんどんパニックに陥ってゆき苦しむのですが、それを通り越すと気分がすっかり良くなるんだそうです。
さらにジョギングを繰り返すことで、症状の改善に繋がると、結論づけています。
ADHDにはジョギング+体を複雑に使う競技を
ADHDを持ってる人にも、ジョギングが有効です。
ただジョギングするよりも、より複雑な体の動きを要するものがピッタリです。ダンスやフィギュアスケート、体操など。
かつては、大人になればADHDは治ると言われていましたが、現在では大人のADHDが認識されています。
運動することで、トラブルが減るとは朗報ではないでしょうか。
ジョギングすれば、学習能率が上がる!
誰にも当てはまるジョギングの効能は、学習能力をアップさせます。
集中力が学習能力に大きく関わります。ジョギングをすると頭が冴える!というのは本当なんです。
女性の悩み…PMSにはジョギングを!
女性は月経の周期に合わせて、心身ともにアップダウンが激しいものです(´;ω;`)
特に、月経前のPMSに悩む女性も多いはず。PMSにももちろん、ジョギングです。
妊娠出産~子育て中の心のトラブルも、ジョギングを
女性のトラブルと言えば、妊娠出産~子育てに至るまで続きます。
妊娠中のジョギングは、赤ちゃんの成長にも関わっているそうです。
さらにさらに、子育てに悩むママたちにも、ジョギングが推奨されています。
加齢……有酸素運動で上手に老いる
老いからは逃れることができません。
ですから、できれば滞り無く歳を取れればいいなぁなんて思いますが、これだけは自然のことですからワカリマセン。
自分の人生ですから、自分で管理しないといけません。加齢にもやはり、有酸素運動が効果的です。
と言っても、ジョギングは足腰に負担がかかりますから、ウォーキングを今のうちから取り入れてみても。
ジョギングしようぜ!の根拠を示すも…難しかった
と、結論だけ言えば「ジョギングしようぜ!」という内容です(笑)
より正確に言うと、「有酸素運動をしよう」という本。
そのために、膨大な実験結果や症例が次から次へと紹介されています。
ちょっと分厚目の本な上に、結構、読み通すのに時間がかかり苦労してしまいました…(・・;)
クライアントの例なども、アメリカでの話ですから、日本の常識や習慣ともやや違う部分もあるかもしれません。
有酸素運動を「続ける」工夫を!
「有酸素運動」の効果が紹介されていますが、もうひとつ大切なこと。
「継続する」続けることが大切です。
継続のために、一人で孤独にチャレンジするよりも、周りの人を誘って大勢で取り組むほうがより効果的です。
励ましたり、励ましあったりできると、忙しい時や面倒なときも、取り組めますね。
あさよるは、SNSを利用するのもいいんじゃないかと思いました。ジョギングした距離や、体重の変化など、多くの人とSNSで発信し合いながらもアリだなと。
無酸素運動ってどうなのよ?
無酸素運動についても、少しだけ言及されていました。
が、どうやら実験が難しいらしく、不確かな要素が多いそうなのです。
しかし、筋トレで、学習効率があがるなどの例はあるそうなのです。これはこれで続けてゆきましょう。
なぜ?なんで?を知りたいあなたへ
本書では有酸素運動の有効性と、ジョギングが推奨されています。
この情報だけで、有酸素運動に取り組もうと思う人には、わざわざ読まなくても良い本ではないでしょうか。
しかし、それより一歩踏み込んで、「なぜ有酸素運動がいいのか」「なぜ運動しないといけないのか」という「なぜ?」の部分を知りたい方は、一読の価値ありだと思います。
症例も数々紹介されているので、人に運動を勧めないといけな立場の人にも良いかもしれませんね。
関連記事
トレーニング・ストレッチの本
- 『2週間で腹を割る! 4分鬼筋トレ』|腹筋を割る。それだけだ
- 『スロトレ完全版 DVDレッスンつき』を読んだよ
- 『すごいストレッチ』|今すぐ!その場でラクになろう~
- 『実はスゴイ四股 – いつまでも自力で歩ける体をつくる』|颯爽と歩く美人に
- 『どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法』|柔軟な体で自信を
ジョギング・ウォーキングの本
- 『正しいウォーキングの始め方』|その歩き方は効いてないかも?
- 『歩き方で人生が変わる』|歩幅と速さでステイタスが変わる?
- 『1日10分歩き方を変えるだけでしつこい肩こりが消える本』
- 『「体幹」ランニング』を読んだよ
姿勢に関するの本
脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方
- ジョン・J.レイティ、エリック・ヘイガーマン
- NHK出版
- 2009/3/20
目次情報
序文 結びつける
◉第一章 革命へようこそ――運動と脳に関するケーススタディ
トップクラスの成績/新しい体育/たいまつを掲げる
新しいステレオタイプ「賢い運動選手」/体にいいことは、脳にもいい
まったく新しい球技/先駆者についていこう/フェットネスを超えて/教えを広める◉第二章 学習――脳細胞を育てよう
メッセンジャー役の物質たち/学ぶことは成長すること/最初のひらめき
環境要因と脳/可塑性を伸ばす/体と心の関係/こんな運動をしよう◉第三章 ストレス――最大の障害
ストレスを定義し直す/ストレス免疫をつけよう/警報システム/燃料を燃やす/知恵
本能と戦う/ストレスはあなたを殺すだけではない/もうたくさん!/ストレスの有害作用
ストレスを燃やし尽くす/心を守るものが体も守る/こんな運動をしよう◉第四章 不安――パニックを避ける
エイミーのケース/防衛/証拠/恐れを恐れる/パニックの苦しみ/苦しみ抜いて
失われたつながり/恐怖に向かって走れ/恐怖から走って逃れる/こんな運動をしょう◉第五章 うつ――気分をよくする
新しいブーム/収束する生化学回路/本物のテスト/最高の処置/論理の穴
裏にある結合/絆を断つ/トンネルを抜ける/こんな運動をしよう◉第六章 注意欠陥障害――注意散漫から抜け出す
とてつもない注意散漫/問題の兆候/大々的に、しかも曖昧に、やり遂げる
全コントロール・ユニット、注目!/初期の手がかり/エクササイズに集中する
脳を関与させる/典型的な事例/こんな運動をしよう◉第七章 依存症――セルフコントロールのしくみを再生する
不当な報い/ふたたび自立する/ドーパミンへの渇望
衝動と戦い、習慣を経つ/ある依存症患者の物語り/ランナーズハイ
よいものにこだわる/空の容器を満たす/こんな運動をしよう◉第八章 ホルモンの変化――女性の脳に及ぼす影響
PMS――自然な変動/バランスを回復する/妊娠――動くべきか、動かざるべきか
赤ちゃんのことをお忘れなく/産後のうつ――青天のへきれき/元の自分に戻る
閉経――大きな変化/運動補充療法/こんな運動をしよう◉第九章 加齢――賢く老いる
すべてをひとつに/いかに年をとるか/認知力の衰え/感情が貧しくなる
認知症/人生のリスト/母の教え/食事――軽く、体にいいものを食べよう
運動――規則正しくつづけよう/頭の体操――学びつづける◉第十章 鍛錬――脳を作る
走るべく生まれついている/ウォーキング/ジョギング/ランニング
非有酸素運動/やり通すこと/大勢でやればなおよい/柔軟性を保つあとがき 炎を大きくする
謝辞
訳者あとがき巻末 用語解説
ジョンJ.レイティ [John J. Ratey]
医学博士。ハーバード大学医学部臨床精神医学准教授。マサチューセッツ州ケンブリッジで開業医としても活躍。研修医訓練の監督補佐を務めるマサチューセッツ精神衛生センターでは10年以上にわたって研修医やハーバード大学医学部学生たちを教える。また、ハーバード大学医師生涯教育プログラムの常勤講師として精神科医たちを教えている。
臨床研究者として精神医学と精神薬理学分野のピアレビュー専門誌に60以上の論文を発表。1986年にはボストン自閉症研究センターを設立、また、攻撃的行動への新しい投薬治療についての彼の研究から、88年にはアメリカ精神医学会に新しく攻撃性に関する研究会が生まれた。
80年代にエドワード・ハロウェル医師とともにADHDの研究を始め、94年に初めてこの障害を分かりやすく説明する著書『へんてこな贈り物』(インターメディカル)を執筆。97年には臨床的障害のより軽微な症例について研究した『シャドー・シンドローム~心と脳と薬物治療』(河出書房新社)をキャサリン・ジョンソン博士との共著で発表。また2001年にはベストセラーになった『脳のはたらきのすべてがわかる本』(角川書店)を刊行し、精神科学が感情や行動、そして心理学全般に与える影響について論じた。
1998年から毎年、同業者の選出による全米ベスト・ドクターのひとりに選ばれ続けている。また最近では、本書のテーマである定期的な有酸素運動の普及に貢献したとして、非営利団体PE4Lifeより最優秀支援賞を受けている。
著者サイト www.johnratey.com
エリック・ヘイガーマン [Eric Hagerman]
サイエンス・エディター。Popular Science 誌、Outside 誌で編集主任を務める。本書ではジョンJ.レイティの執筆・構成をサポートした。
野中 香方子(のなか・きょうこ)
翻訳家。お茶の水女子大学教育学部卒業。主な著書にグレゴリー・バーンズ『脳が「生きがい」を感じるとき』、マシュー・ブレンジンスキー『レッドムーン・ショック』(ともにNHK出版)、クレイグ・ベンター『ヒトゲノムを解読した男』、ジョン・ホイットフィールド『生き物たちは3/4が好き』(ともに化学同人)、ユージン・リンデン『動物たちの愉快な事件簿』(紀伊國屋書店)、ナイルズ・エルドリッジ『ヒトはなぜするのか』(講談社インターナショナル)、共訳書にレイ・カーツワイル『ポスト・ヒューマン誕生』(NHK出版)、リチャード・フォーティ『地球46奥年全史』(創始者)などがある。



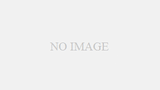
コメント
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 記事リンク:『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 記事リンク:『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 記事リンク:『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 記事リンク:『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『スタンフォード式 最高の睡眠』|充実した仕事・私生活のための […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]
[…] 『脳を鍛えるには運動しかない!―最新科学でわかった脳細胞の増やし方』 […]