家族、同僚、ネットのともだち……
みんな「強いつながり」ばかり。
こんにちは、あさよるです^^
東浩紀さんの著書をかつて、数冊手に取ったことがあったのですが、そのときは「なんのこっちゃ」と分からずに、数ページで投げ出してしまいました(苦笑)。
今回、東浩紀さんの『弱いつながり』はSNSにて知人が紹介していたので、手に取ってみましたが……。「最後まで読めるのかしら」と不安な読書の始まりでした(^_^;)
あれ?インターネットってこんなだった?
誰もがスマホを持ち、いつでもどこでもインターネットにアクセスできるようになりました。いつでもどこでも世界中の情報にアクセスできるのですから、それはそれは便利にな……りましたか?
SNSを通じて、これまでとは全く違う生い立ちや背景の人と繋がれ……ましたか?
あれ?インターネットって、これまで見たこともないようなワクワクドキドキ好奇心が止まらないモノだと思ってたのに、いつの間に、「いつもと同じような」メンツと、いつもと同じようなブログやサイトを閲覧するようになったんだろう?
そういえば「ネットサーフィン」なんて言葉も聞かなく&使わなくなりました。
調べ事をしようとGoogle検索すると、Googleはアルゴリズムを使って、自分が好きそうなページを検索上位に表示します。
SNSでは、自分がお友達登録をしたアカウントの情報しか流れてきません。TwitterもFacebookもそうです。「自分」という人物のフィルターを通しているので、それ以外の人と繋がりが持てません。
インターネットはどんどん、自分と似た、自分と親しい、自分の好きな人や情報としか繋がれないものとなっています。
ネットの「強いつながり」からリアルへ
インターネットにより部屋に居ながらにして世界と繋がり、見聞が広がるだろうと予想されました。
が、実際には、インターネットは自分が見たいものしか見えない、知りたいことしか知れないツールです。
しかも、思考がより濃密に凝縮されてゆくツールです。SNSでフォローしているアカウントは、みな自分の思想や心情が近い人ばかり。目障りな人や意味不明な人は、ブロックやミュートしてしまいます。
すると、どんどん自分と同じ思想を持つ人ばかりと繋がるようになる。Google検索すれば、アルゴリズムにより自分の思考に沿った検索結果が現れる。ますます、思考や思想が濃く、狭くなってゆく。
東浩紀さんの『弱いつながり』では、思考が狭まってしまうのを防ぐため、物理的な位置を動かしてしまおうと勧めています。
すなわち、旅に出る!
しかも、バックパッカーなような旅ではなく、「観光客」になろう。
軽薄な観光客になろう
旅行代理店やパックツアーを使っても良いでしょう。軽薄な、表層しか見ない観光客になりましょう。
バックパッカーのような旅は、やはり敷居が高いというか、ある一定の条件を満たせる人じゃないと難しいでしょう。例えば、小さな子供いる家族旅行では無理だし、まとまった休暇が取れる人じゃないと難しい。
現在「観光」というと、ちょっとミーハーな雰囲気があるのでしょうか。「どうせ上っ面しか見ないんだったら、行かないほうがマシだ」と思う人もいるそうです。
しかし、「百聞は一見にしかず」という言葉があります。
『弱いつながり』では、東浩紀さんご自身の旅行の経験が数々紹介されています。東さんは、ツアーメニューとして、アウシュビッツへ赴かれたそうです。そこで、観光地化された施設への驚きとともに、生々しい「死」にも驚かれたそうです。
あくまで観光客として訪れた地ですが、その一回の経験でその後の考え方まで大きく影響を与える出来事でした。
「観光客」と言うと、なんだかミーハーな響きにも聞こえますが、たった一回、上辺だけなでる「観光客」だって、「百聞は一見にしかず」を実感できます。
「憐れみ」をキーワードに
インターネットの濃い繋がりでは、どんどん思想が偏ってしまいがちです。自分の考えや自分の好みなものばかり表示されるのですから、視野が狭くなってゆくばかり。
差別発言を平気でしまくる人や、「◯◯は死ねばいい」「△△は殺してしまえ」なと、過激で突飛な発言を繰り返す人がいます。
しかし、そのような発言をする人だって、目の前で人が倒れていれば、駆け寄って声をかけるでしょう。この時、国籍を問うて助けるか助けないか考えたりしないでしょう。
そこにあるのは、目の前の人物に対する「憐れみ」です。
頭の中にある考えと、実際に目の前で起こることには隔たりがあります。
どこの誰かへ向ける「憐れみ」を本書では「弱いつながり」と呼びます。家族や親類、あるいはインターネットがもたらした「強いつながり」から離れ、人としての「憐れみ」を持ち、「弱いつながり」のある世界へ旅しましょう。
グローバリゼーション
旅先では、グローバリゼーションにも出会います。
アジアの都市は近代化が進み、西洋的な建築もたくさん立ち並びます。日本の都市もみなそうですね。
しかし、同じアジア圏の西洋化といっても、その国その国によって「違い」があります。その「違い」こそが、他のものに取って代われない、その国独自の文化なのかもしれません。
また、「東京」を模倣した商業施設もあります。西洋化された東京の街を、さらに模倣するという、段階を踏むことで、新たな文化が生まれようとしています。面白いですね。
旅行嫌いのあさよるには……
実のところ あさよるは、旅行はあまり好きではありません。用意や、荷造りや荷解きが面倒です(苦笑)。
たまには、日帰りのパックツアーなら行ってもいいかなぁと思いますが、一泊となると嫌だなぁw
なるべく家から出ずに生きたい あさよるとしては、『弱いつながり』は耳の痛い話でした。
なぜなら、『弱いつながり』の主張は真っ当なものだと感じたからです。ダラダラと本を読んだりYouTubeを見ていても、楽しく毎日やっていけます。
ただし、絶対的な経験値不足に陥ってしまわないかと、実は内心恐れていたところを、図星されちゃいました。
関連記事
- 14歳からの社会学 これからの社会を生きる君に
- チームで挑め!『君に友だちはいらない』
- 『年収150万円で僕らは自由に生きていく』|「少ないお金でもなんとかなる」に
- 『これからの「正義」の話をしよう』|ヒーロー?犯罪者?法の裁きは「正義」?
- 安心社会から信頼社会へ 日本型システムの行方
弱いつながり 検索ワードを探す旅
- 東浩紀
- 幻冬舎
- 2014/7/24
目次情報
0|はじめに|強いネットと弱いリアル
1|旅に出る|台湾/インド
2|観光客になる|福島
3|モノに触れる|アウシュヴィッツ
4|欲望を作る|チャルノブイリ
5|憐みを感じる|韓国
6|コピーを恐れない|バンコク
7|老いに抵抗する|東京
8|ボーナストラック|観光客の五つの心得
9|おわりに|旅とイメージ
東 浩紀(あずま・ひろき)
1971年東京都生まれ。作家、思想家。株式会社ゲンロン代表取締役。『思想地図β』編集長。東京大学教養学部教養学科卒、同大学院総合文化研究博士課程修了。1993年「ソルジェニーツィン試論」で批評家としてデビュー。1999年『存在論的、郵便的』(新潮社)で第21回サントリー学芸賞、2010年『クォンタム・ファミリーズ』(河出文庫)で第23回三島由紀夫賞を受賞。他の著書に『動物化するポストモダン』『ゲーム的リアリズムの誕生』『ゲーム的リアリズムの誕生』(以上、講談社現代新書)、『一般意志2.0』(講談社)、「東浩紀アーカイブス」シリーズ(河出文庫)、『クリュセの魚』(河出書房新社)、『セカイからもっと近くに』(東京創元社)など多数。また、自らが発行人となって『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』『福島第一原発観光地化計画』(ゲンロン)も刊行。



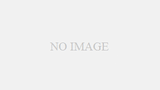
コメント
[…] 記事リンク:『弱いつながり 検索ワードを探す旅』|弱くて軽薄な憐れみを […]
[…] 『弱いつながり 検索ワードを探す旅』|弱くて軽薄な憐れみを […]
[…] 『弱いつながり 検索ワードを探す旅』|弱くて軽薄な憐れみを […]
[…] 『弱いつながり 検索ワードを探す旅』|弱くて軽薄な憐れみを […]
[…] 『弱いつながり 検索ワードを探す旅』|弱くて軽薄な憐れみを […]