こんにちは。休むのが下手なあさよるです。
いや、自分ではポジイティブに「頑張り屋さんです☆」「真面目なんですっ♡」って解釈するようにしてるんですけど……いや、無理がある……!?
2016年の大河ドラマ『真田丸』を毎週見てるんですけどね、堺雅人さん演じる真田幸村も、よく言えば「頑張り屋」。悪く言えば「休むのが下手だなぁ」と思い、妙な親近感を感じます。
人に頼まれると承諾しちゃうんだよなぁ~。お調子者なのだなぁ……チーン
とりあえず、一つだけわかることは、あさよるもここままだと、やられてしまうってこった!
誰も彼も睡眠不足!
はてさて『休む技術』。タイトルがそのまんまです。年中過労気味のあよるには耳の痛いタイトルです。
休むことはとても大切です。「言われなくてもわかってるよ!」と言いたいところですが、その通りに休めていますか?
データによると、日本人のどの年代を通じても睡眠不足気味です。中でも40代の働き盛りの人たちの睡眠不足は顕著。
もちろん、それだけ多忙を極めているからなのですが、きちんと休まないと、終わる仕事も終わりません。
本書『休む技術』の主張は単純です。「休みなさい!」これだけ。だけど、そのひと言を実行するのがどんなにも難しいか!
しかし、それを押してでも休まねばならない。
まずは「休めない」というメンタルブロックを解く。少しでも意識が変わるよう何度も何度も、手を変え品を変え読書に語りかけます。
実際に「休む技術」が身につくか?
『休む技術』というタイトルですが、正直この本を読んで実際に上手に休める用になる人は少数でしょう。
というか、元々上手に休めている人と、休むのが下手な人の差は、本を読んだくらいでは変わらないのではないかと……(-_-;)
しかし、あさよる自身が休むのが下手な人なもんで、次から次へ休むための方法を提示さて続けると、耳が痛く、そして、「確かに、休もうと思えばいくらでも休めるのになぁ」と自分自身に問いかけていましたw
旅行に行く。泊まりが無理なら日帰り旅行へ。半休でも休める。ちょっとの時間でも休める。こんな風に畳み掛けられると、「まぁ、ほんとは休めないほど多忙じゃないよなぁ…」と根負けする感じですw
しかし、まずは「自分には休みが足りない」ということ。そして「その気になれば休める」と自らが気づかずにどうしようもありません。
病気を防ぐあの手この手
著者は精神科医で、専門家ならではの話もあります。
近年増え続ける「うつ」も、休むことが大切です。しかし、まじめな人ほど休むのが下手。
一旦、仕事を休職し、通院しながら職場復帰した患者さんの中には、平日は働けるけど週末になると何をすればよいかわからず気分が滅入ってしまう人もいるそう。
そんな患者さんに、精神科医の著者は話しかけるように、ページは進みます。
「ホッと一息」も立派な休憩。また、家でジッとすることのみが休むことではありません。
ショッピングへでかけたり、気分転換に映画を見に行ったり日帰り旅行をしたり、動の休養というものもあるんですね。
気分転換が苦手な人へ
『休む技術』は、休むのが下手な人、気分転換を上手にできない人にぴったりの本です。
くれぐれも、この本を読んだからって体が休まるわけじゃないし、読むだけで上手に休めるようになるわけでもありません。
あくまで、「休む」ことがとんでもなく大事なことであること、そして、「積極的に休まないと休めない」ことを知りました。
ある日突然、天から「休み」が降ってくるのではなく、自分で意識して、積極的に「休み」を作り出さないといけない。
もし、休まないことで体調不良や能率低下が起こった時、それは自分の管理不足です。人のせいにはできません。
だから、変な話だけれども「頑張って休もう」と思いましたw
関連記事
西多昌規さんの本
疲労回復や休息に関する本
- 『最高の休息法』|脳科学×瞑想で集中力が高まる
- 『すべての疲労は脳が原因』|パフォーマンス低下してるなら
- 『スタンフォード式 疲れない体』|効率よく活動し、疲労を持ち越さない体に
- 『最高の疲労回復法』|疲労→回復サイクルへ
- 『体力の正体は筋肉』|筋トレは裏切らない
- 『スタンフォード式 最高の睡眠』|充実した仕事・私生活のための
- 『「早起き」の技術』|タイムスケジュールはできてるか
休む技術
- 西多昌規
- 大和書房
- 2013/5/22
目次情報
はじめに
1章
暮らしをゆるめてこまめに休む技術せっかく休んでも、休んだ気になれないのはなぜ?
・休日を楽しめなくなっていませんか?
・リズム変えず、楽しみを付け足す感覚で「仕事の不安」が楽しみをつまらなくしている
・「週末うつ」にならない休日の過ごし方
・一流のクリエーターはリフレッシュも上手平日に、5分スポット「好きなこと時間」を確保する
・「静」だけが休むことではありません
・ほっとひと息のメニューを用意しましょう仕事の中に「サボる時間」を「計画」すればラクになる
・疲れて効率が落ちるより、ちゃんとサボるほうがいい
・前もって、半休申請してしまうのが効果的「面倒くさい」ことは、「とりあえず」始めてみる
・なぜ、面倒なことを始められないのか?
・手足や指を動かすだけで「やる気スイッチ」が入る「楽しいこと」への期待感をもち続ける
・休みを「楽しみにする」ことでもっと楽しくなる
・喜びの予感が喜びを生むカレンダーの休日を見ながら楽しめそうなプランを考える
・旅行プランは早く考えるほど「吉」
・遊びにも、通年スケジュールを取り入れよう他人のプランに乗っかって、新鮮な休日をプランニングする
・「非日常」が新鮮な休日の合言葉
・汗をかく、旅行に行く、映画館のはしご、初めてのエステ……まずは、来月の「カジュアル旅行」の予定を決める
・旅行は楽しい。でも、準備が大変?
・「本格旅行」より手軽な「カジュアル旅行」なら気軽に行けるいつものオフにサムシングニューをプラスする
・大人の定番オフは、リラックス効果満点!
・プラスαの「お楽しみ要素」をひとつ取り入れるブレイクタイム
映画、観劇、コンサート、楽器や絵画、手の込んだ料理……
2章
からだをゆるめて休ませる技術その眠気、「睡眠不足症候群」です
・働き盛りは男女ともに睡眠不足のひとばかり
・「寝る時間を早くする」のはなかなか難しい?睡眠の取り方を変えれば、パフォーマンスを上げられる
・まずは、快眠の基本を押さえましょう
・「時計遺伝子」は規則正しい食事と運動で発動する「ダルい」「しんどい」のもとにある「慢性疲労」はゆるいスポーツで改善する
・「かったるい」が口癖になっていませんか?
・意外かもしれませんが、からだは動かしたほうが疲れません道具を使うスポーツやラジオ体操・ヨガはなぜ、こころとからだにいいのか
・脳の運動系を刺激すると神経細胞が活性化する
・「走る」「歩く」以外のゲーム性を楽しめる運動をマッサージは疲れた「あと」より「前」がお勧めです
・疲労物質を分解するには「すぐあと」が効果的
・リラックスしてウトウト……がマッサージの理想すきま時間の「5分間瞑想」でこころとからだを蘇らせる
・家でも仕事場でも簡単にできる「瞑想」で気持ちをリセット
・お昼休みのちょこっと瞑想で、午後からはリフレッシュ疲れをごまかす脳のはたらきがこころの疲労骨折のもとになることも
・疲れたことに気づかれない「疲れ」が増えています
・「ハイテンション」と「うつ」の危険な関係ブレイクタイム
ホテルで何もしない時間をつくる、リゾート・海外旅行の楽しみ方
3章
上手に休んでパフォーマンスを上げる技術仕事モードをリラックスモードに一瞬で変える方法
・脳のモードを切り替えてのんびり休むには
・複式呼吸でリラックスのスイッチを入れる休憩でワーキングメモリの機能をチャージする
・忙しいと、記憶・判断・感情コントロール能力さえも「失って」しまう
・リラックスすればワーキングメモリも回復する15分の仮眠でワーキングメモリを生き返らせるには
・睡眠不足はワーキングメモリの大敵
・無理を続けるほど失敗のリスクは高まるこころの余裕が集中力を高めてひらめきを生む理由
・へとへとになるまで頑張っても、アイデアは湧いてこない
・まず、休んでから考えよう休憩か? 仕事か? と迷ったときには……
・記憶力にもやっぱり「息抜き」が大事
・休むことで、記憶は脳に定着するメリハリの「メリ」が「長く」「ストレスなく」頑張れるコツ
・頑張り続けるよりも力を抜くテクニックが大事
・「メリ」と「ハリ」のメリットを交互に得られるイメージトレーニング仕事の「CMタイム」はどのくらい必要?
・自分のからだなのに、どれくらい疲れているのかわからない?
・集中して仕事をするために必要な休息の目安は?ブレイクタイム
・ガーデニング、トレッキング……自然の癒しの力を満喫しよう
西多 昌規(ひしだ・まさき)
精神科医・医学博士。自治医科大学精神科医学教室・講師。
1970年、石川県生まれ。東京医科歯科大学卒業。
国立精神・神経医療研究センター、ハーバード・メディカル・スクール研究員を経て、現職。
日本精神神経学会専門医、睡眠医療認定医など、資格多数。
スリープクリニック銀座でも診療を行うほか、企業の精神科産業医として、メンタルヘルスの問題にも取り組んでいる。
著書に『「昨日の疲れ」が抜けなくなったら読む本』『「月曜日がゆううつ」になったら読む本』(大和書房)、『「テンパらない」技術』『「凹まない」技術』(以上、PHP文庫)、『今の働き方が「しんどい」と思ったときのがんばらない技術』(ダイヤモンド社)、など多数。



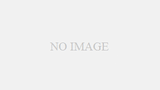
コメント
[…] 記事リンク:『休む技術』|頑張って休もう!?「動の休み」もあるんです […]
[…] 記事リンク:『休む技術』|頑張って休もう!?「動の休み」もあるんです […]
[…] 『休む技術』|頑張って休もう!?「動の休み」もあるんです […]
[…] 西多昌規さんの本:『休む技術』|頑張って休もう!?「動の休み」もあるんです […]
[…] 『休む技術』|頑張って休もう!?「動の休み」もあるんです […]
[…] 関連記事:『休む技術』|頑張って休もう!?「動の休み」もあるんです […]
[…] 西多昌規さんの本:『休む技術』|頑張って休もう!?「動の休み」もあるんです […]