こんにちは。豆乳、枝豆を毎日投入していたら(ダジャレ)、体がモチモチになった あさよるです。
タンパク質スゴイ!あさよるの体も、あさよるの食べたもので出来てるんだなぁと実感。
「動的平衡」とは
以前、『せいめいのはなし』という本を読みまして、その本のなかで「動的平衡」という言葉が使われていました。
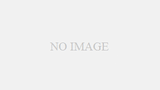
それは一体なんじゃろ?と、同著書の、ズバリ『動的平衡』という本を見つけたので読んでみました。
本書内に「動的平衡」の説明があったので引用します。
エントロピーとは「乱雑さ」の尺度で、錆びる、乾く、壊れる、失われる、散らばることと同義と考えてよい。
秩序あるものはすべて乱雑さが増大する方向に不可逆に進み、その秩序はやがて失われてゆく。
(中略)
生命はそのことをあらかじめ織り込み、一つの準備をした。エントロピー増大の法則に先回りして、自らを壊し、そして再構築するという自転車操業的なあり方、つまり「動的平衡」である。
しかし、長い間、「エントロピー増大の法則」と追いかけっこしているうちに少しずつ分子レベルで損傷が蓄積し、やがてエントロピーの増大に追いつかれてしまう。つまり秩序が保てない時が必ず来る。それが個体の死である。
(中略)
したがって「生きている」とは「動的な平衡」によって「エントロピー増大の法則」と折り合いをつけているということである。『動的平衡』p.245-246
生命とは、絶対的な決まった形のあるものではなく、瞬間瞬間の化学変化の連鎖によって維持されています。
さらに引用します。
生体を構成している分子は、すべて高速で分解され、食物として摂取した分子と置き換えられている、体のあらゆる組織や細胞の中身はこうして常に作り替えられ、更新され続けているのである。
だから、私たちの身体は分子的な実態としては、数か月前の自分とはまったく別物になっている。分子は環境からやってきて、一時、淀みとして私たちを作り出し、次の瞬間にはまた環境へと解き放たれてゆく。
(中略)
つまり、そこにあるのは、流れそのものでしかない。その流れの中で、私たちの身体は変わりつつ、かろうじて一定の状態を保っている。その流れ自体が「生きている」ということなのである。『動的平衡』p.231-232
「動的平衡」のかみ砕かれた内容
本書『動的平衡』は、環境雑誌『ソトコト』で連載されていたものだそうです。
ですから、生命や生物学的な専門の話というよりは、「動的平衡」をテーマとしたコラム集のようです。
ですから、どなたが読んでも理解できる内容です。
生命そのものの話だけでなく、ダイエットや健康志向について、食品問題、そして病気など、展開されます。
あさよる的には「動的平衡」について科学的な話を期待していたので、求めていた内容とは違いました。
ですが、特に食品やサプリメントについての話題は、他人事ではないので興味惹かれました。体の仕組みも、食品についても何も知らないのに、“サプリペンと頼み”みたいになってるかも……反省。
これから読むなら『生物と無生物のあいだ』で
先に引用した通り、生物は流れそのものでしかなく、その流れの淀みである。改めて話を整理されて伝えられるとねぇ。
「そうだったのか……orz」
いやね、多くは以前読んだ『せいめいのはなし』や『生物と無生物の間』でも語られていました。
もし、これから読まれるんだったら、『生物と無生物のあいだ』でいいかも。与太話的な要素もほしいなら、『せいめいのはなし』はハイレベルな対談集ですから、楽しですよ。
関連記事
- 『せいめいのはなし』|「生命」をテーマのダベリはおもしろい
- 『カラー版 細胞紳士録』|私の中の頼もしい紳士たち!カラー写真で
- 『ウイルスは生きている』|たんぱく質の結晶は、生命か!?
- 『ゾウの時間 ネズミの時間』|車輪を持つ生きものがいないのはなぜ?
- 『カラダが変わる! 姿勢の科学』を読んだよ
動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか
- 福岡伸一
- 木楽舎
- 2009/2/17
目次情報
「青い薔薇」――はしがきにかえて
プロローグ――生命現象とは何か
第1章 脳にかけられた「バイアス」
――人はなぜ「錯覚」するか第2章 汝とは「汝の食べた物」である
――「消化」とは情報の解体第3章 ダイエットの科学
――分子生物学が示す「太らない食べ方」第4章 その食品を食べますか?
――部分しか見えない者たちの危険第5章 生命は時計仕掛けか?
――ES細胞の不思議第6章 ヒトと病原体の戦い
――イタチごっこは終わらない第7章 ミトコンドリア・ミステリー
――母系だけで継承されるエネルギー産出の源第8章 生命は分子の「淀み」
――シェーンハイマーは何を指揮したかあとがき
福岡 伸一(ふくおか・しんいち)
1959年東京生まれ。京都大学卒。米国ロックフェラー大学およびハーバード大学医学部博士研究員、京都大学助教授を経て、青山学院大学理工学部教授。分子生物学専攻。専門分野で論文を発表するかたわら一般向け著作・翻訳も手がける。2006年、第1回科学ジャーナリスト賞受賞。著書に、『プリオン説はほんとうか?』(講談社ブルーバックス 講談社出版文化賞科学出版賞)、『もう牛を食べても安心か』(文春新書)、『ロハスの思考』(木楽舎ソトコト新書)、『生命と食』(岩波ブックレット)、『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書 2007年サントリー学芸賞)。翻訳に、ノーベル平和賞受賞者ワンガリ・マータイ氏の自伝『モッタイナイで地球は緑になる』、テオドル・ベスター氏の『築地』(ともに木楽舎)など。近著に『できそこないの男たち』(光文社新書)。



コメント
[…] 『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』|生命とは、流れのなかの淀み […]
[…] 『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』|生命とは、流れのなかの淀み […]
[…] 『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』|生命とは、流れのなかの淀み […]
[…] 『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』|生命とは、流れのなかの淀み […]
[…] 『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』|生命とは、流れのなかの淀み […]
[…] 福岡伸一『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』|生命とは、流れのなかの淀み […]